 「ブログは人を表す」と誰かが云ってるかは知らないが、少なくとも当ブログには私の興味対象の多くが記載されている。書きたくても書けない事柄もあるので、もろちんこれがすべてではない。念のため(笑)。日本映画についての記事が多いのは、ウェブサイトでやるほど映画に詳しくないからで、とりあえず観た映画のことを書いている。なぜ、日本映画なのかと云えば、映画に映る風景や街並みの変遷が面白いからだ。映画に映り込んでくる昔のクルマや交通機関、電気製品、建築や土木構造物、看板や家具や衣装のデザイン、そんなものを見ながら楽しんでいることの方が実は多い。そこには当然ノスタルジックな感慨も含まれるが、必ずしも自分が生きた時代や知る風景でなくとも面白いと感じているところからすると、歴史的地理的あるいは文化人類学的な?興味で映画を観ているのかも知れない。だから、私は大規模なオープンセットで完璧な人工的空間を構築するハリウッド映画にはほとんど興味がなく、むしろ低予算がゆえに東京やその周辺でのロケでお茶を濁している日本のB級映画の方がかつての時代が映り込んでいるので大好きだったりする。もちろん、自分の住む地域が映っていれば興味は当然倍増だ。ストーリーはまあ見ていて飽きなければとりあえずOK。もちろん面白かったら当たりだとは思う。大作よりも娯楽作品や「流行に乗って作っちゃいました」みないなものが案外好きだ。正直、映画には詳しくないので偉そうなことは書けないが、強いて云えばその映画に映る時代に映画人がどう生きたのか?キャストやスタッフの生き様には多少興味がある。映画人の自伝評伝は出来るだけ読むようにもしている。俳優に対する興味も基本的には軽い。現在は御老人になられた男優さんたちの若かりし頃の雄姿を見るのは単純に嬉しいし、シワだらけのお婆さんになった女優さんの美しい娘時代を映画で観られるのも至上の喜びだ。むしろその美しかった貴重な一瞬にときめいたり魅かれたりもする。むろん、今でも綺麗ならそれはそれで云うことはない。(笑) 女優といえば私の一番のお気に入りは芦川いづみさん。今から40年ほど前、藤竜也さんと結婚し引退してしまった日活の女優さんだ。年齢的には自分の母親ほど(^_^)。芦川いづみさんの何処が良いかってそれは映画で見てもらうしかないのだが、若き日はひたすら可愛くその後はひたすら誠実に仕事仕事・・・。同僚からも好かれ、映画が斜陽になったら結婚退社。まあ足跡を見れば一昔前の女性像そのままなのだけれど、なんてたって彼女は故石原裕次郎氏の相手役なのだ。自分の世代も含めて若い人々にはあまり知られていないが、それはスーパーの付くスター女優だってことを意味する。ブルジョアと庶民、スターと一般人の差がまだ明確だった昭和30年代、控えめな彼女もドル360円のその時代に日本では誰も使っていないようなフランス直輸入の化粧品でメークをし、自分で外車を乗り回していたのだから面白いし痛快ではないか。それでも彼女からは「女優業を休んでしぱらくパリでお勉強してました」みたいな実力派大女優さんたちにはありがちなアートな嫌味をまったく感じない。そこが好きなのだ。同時期やあるいはその後に、同じようにアイドル的なデビューをし、映画が斜陽になった後も舞台やテレビで研鑽を積み、名実共に大女優となった方々と彼女を比較するのは双方に失礼だと思うが、100本を越える彼女のフィルモグラフィーは可憐さと誠実さに満ちていると私は思う。映画に詳しいお歴々が何と云おうと私は女優芦川いづみさんが大好きだと云っておこう。さて、現在の芦川いづみさんだが、もともと控えめな方と思われるのとストイックな御主人のお考えもあってかメディアに登場することはまずない。最近の消息と云えば、先日、御主人が徹子の部屋に出演し、黒柳さんの巧妙な話術に乗せられた御主人により、一緒に陶芸を楽しんでいる由が伝わった程度。もちろん、軽薄なテレビ番組などになんぞには出て欲しいとは私もまったく思わないが、年齢も年齢なのでそろそろ文筆やオーディオコメンタリーなどでかつてのお仕事について語って貰えればなあ~と心から思う。それは週刊誌的な興味からではなく、最近ようやく再評価の兆しが見えてきた日本の青春映画を含む娯楽映画についてを語る時、芦川いづみさん自身の証言はやはり貴重なのではないのかな~と思うからだ。藤さん何卒お願いします(^_^;。
「ブログは人を表す」と誰かが云ってるかは知らないが、少なくとも当ブログには私の興味対象の多くが記載されている。書きたくても書けない事柄もあるので、もろちんこれがすべてではない。念のため(笑)。日本映画についての記事が多いのは、ウェブサイトでやるほど映画に詳しくないからで、とりあえず観た映画のことを書いている。なぜ、日本映画なのかと云えば、映画に映る風景や街並みの変遷が面白いからだ。映画に映り込んでくる昔のクルマや交通機関、電気製品、建築や土木構造物、看板や家具や衣装のデザイン、そんなものを見ながら楽しんでいることの方が実は多い。そこには当然ノスタルジックな感慨も含まれるが、必ずしも自分が生きた時代や知る風景でなくとも面白いと感じているところからすると、歴史的地理的あるいは文化人類学的な?興味で映画を観ているのかも知れない。だから、私は大規模なオープンセットで完璧な人工的空間を構築するハリウッド映画にはほとんど興味がなく、むしろ低予算がゆえに東京やその周辺でのロケでお茶を濁している日本のB級映画の方がかつての時代が映り込んでいるので大好きだったりする。もちろん、自分の住む地域が映っていれば興味は当然倍増だ。ストーリーはまあ見ていて飽きなければとりあえずOK。もちろん面白かったら当たりだとは思う。大作よりも娯楽作品や「流行に乗って作っちゃいました」みないなものが案外好きだ。正直、映画には詳しくないので偉そうなことは書けないが、強いて云えばその映画に映る時代に映画人がどう生きたのか?キャストやスタッフの生き様には多少興味がある。映画人の自伝評伝は出来るだけ読むようにもしている。俳優に対する興味も基本的には軽い。現在は御老人になられた男優さんたちの若かりし頃の雄姿を見るのは単純に嬉しいし、シワだらけのお婆さんになった女優さんの美しい娘時代を映画で観られるのも至上の喜びだ。むしろその美しかった貴重な一瞬にときめいたり魅かれたりもする。むろん、今でも綺麗ならそれはそれで云うことはない。(笑) 女優といえば私の一番のお気に入りは芦川いづみさん。今から40年ほど前、藤竜也さんと結婚し引退してしまった日活の女優さんだ。年齢的には自分の母親ほど(^_^)。芦川いづみさんの何処が良いかってそれは映画で見てもらうしかないのだが、若き日はひたすら可愛くその後はひたすら誠実に仕事仕事・・・。同僚からも好かれ、映画が斜陽になったら結婚退社。まあ足跡を見れば一昔前の女性像そのままなのだけれど、なんてたって彼女は故石原裕次郎氏の相手役なのだ。自分の世代も含めて若い人々にはあまり知られていないが、それはスーパーの付くスター女優だってことを意味する。ブルジョアと庶民、スターと一般人の差がまだ明確だった昭和30年代、控えめな彼女もドル360円のその時代に日本では誰も使っていないようなフランス直輸入の化粧品でメークをし、自分で外車を乗り回していたのだから面白いし痛快ではないか。それでも彼女からは「女優業を休んでしぱらくパリでお勉強してました」みたいな実力派大女優さんたちにはありがちなアートな嫌味をまったく感じない。そこが好きなのだ。同時期やあるいはその後に、同じようにアイドル的なデビューをし、映画が斜陽になった後も舞台やテレビで研鑽を積み、名実共に大女優となった方々と彼女を比較するのは双方に失礼だと思うが、100本を越える彼女のフィルモグラフィーは可憐さと誠実さに満ちていると私は思う。映画に詳しいお歴々が何と云おうと私は女優芦川いづみさんが大好きだと云っておこう。さて、現在の芦川いづみさんだが、もともと控えめな方と思われるのとストイックな御主人のお考えもあってかメディアに登場することはまずない。最近の消息と云えば、先日、御主人が徹子の部屋に出演し、黒柳さんの巧妙な話術に乗せられた御主人により、一緒に陶芸を楽しんでいる由が伝わった程度。もちろん、軽薄なテレビ番組などになんぞには出て欲しいとは私もまったく思わないが、年齢も年齢なのでそろそろ文筆やオーディオコメンタリーなどでかつてのお仕事について語って貰えればなあ~と心から思う。それは週刊誌的な興味からではなく、最近ようやく再評価の兆しが見えてきた日本の青春映画を含む娯楽映画についてを語る時、芦川いづみさん自身の証言はやはり貴重なのではないのかな~と思うからだ。藤さん何卒お願いします(^_^;。
記事一覧
藤さん何卒お願いします(^_^;
トリプルプレイで攻撃終了?
「通信と放送の融合」のことをIT業界では「トリプルプレイ」と呼ぶらしい。具体的には「単一の事業者が、電話、通信、放送の3つのサービスを同時に行うこと」を指すようだ。光ファイバ網が都市部をカヴァーしつつある昨今、それは既に一部地域では実現もしている。我家もBフレッツに加入、光電話を使い、フレッツ.NETはともかくGyaoあたりは時折観ており、一応トリプルプレイとやらを享受していることになるのだが、正直なところ「だから何なの?」ってな感じがしないでもない。Bフレッツになりネットサーフィンもファイルのダウンロードも速くなり、すごぶる快適にはなった。光電話はCMのように受話器が光りはしないが、とりあえず今までとほぼ同じように電話が使えて安い。そして注目のブロードバンドコンテンツ。ネットテレビの高品質動画はコマ落ちすることもなく再生され、それはそれは見事な画質で驚いた。暇な正月、TV BankというSoftBankの運営のサイトでNHKの「プロジェクトX挑戦者たち」が1.5Mbpsの高画質で2本配信されているのを見付け、主役がそれぞれ千曲市出身で現松本市長の菅谷昭さんの「チェルノブイリの傷 奇跡のメス」と、坂城町出身でイトーヨーカドーとセブンイレブン(セブン&アイHLDGS.)の代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)、鈴木敏文さんの「日米逆転!コンビニを作った素人たち」だったりしたものだから、食い入るように観てしまった。特に後者の方は知る人ぞ知る「しもざわ酒店」まで写真出演するオマケ付き。個人的には大感動だったのだが、よく考えれば、いや考えなくてもそれはNHK総合が数年前に放送した番組だよな。オリジナルコンテンツではない。USENが運営するGyaoではサザンオールスターズの横浜アリーナでの年越しライブが丸ごと楽しめた。正にトリプルプレイ元年に相応しい豪華なコンテンツではないか。不肖私もプログレヲタクにもかかわらず、一部早送りしながら全て観たが、調べりゃこれもWOWOWの制作で既に衛星で年越し生放送されたもの再放送コンテンツだった。電話は電話のまま、ネットは速くなっただけ。放送は再放送。それを「トリプルプレイ」と云うんだろうか? それともこれは過渡期の状況で、ブロードバンドがさらに普及ればもっと状況が変わってくるのだろうか? それでも状況が変わらなければ、「国に保護された放送局が電波を独占しているのが不公平で失敗した」とでも弁解するのだろうか? 人の事を云えるような身分ではないが、まあ仮にその程度のことであったのなら、IT業界の人々は明らかにコンテンツ創造力が乏しいと思う。古い映画や既存テレビの再放送だけでは、レンタルビデオ店や衛星放送局は潰れても地上波テレビ局はあまり困らない。既存テレビ局にとってそのあたりは既にケーブルテレビや衛星放送、レンタルビデオチェーンに奪われてしまったシェアに過ぎない。昨今、大手レンタルビデオチェーンに行けばひとつの店に何万本ものソフトが置いてあるが、仮にそのレンタル料が無料だったとしたら、あなたは毎日一年365日ビデオを借りるだろうか? 当然そんな暇は無いだろう。では、それが自宅に居ながらにして選んで観れたとしたら毎日観るだろうか? ニートさんならともかくあなたが勤労者だったらやっぱりそんな暇は無いだろう。問題は時間だけではない。仮に何万本ものソフトが自由に観られても、そんな立て続けに観たいと思うソフトなど無いのが普通だ。もっと即時性のあるもの、例えばニュース。実はこれは既にオン・デマンド化されている。最新の映像ニュースは各テレビ局のサイトやGyaoでビデオクリップになっているのだが、私はほとんど見ない。文字化されたニュースはWEBはもちろんRSSリーダーで読んだりするが、余程の衝撃映像を伴ったニュースでない限り、いちいちひとつひとつの映像を再生して見聞きすることはない。とりあえずビデオ・オン・デマンドの現実なんてそんなものだ。さて、ネットテレビは再放送ばかりなどと書いてしまったが実はGyaoにはオリジナルコンテンツもある。これはある意味重要だ。その代表例が「久米宏のCAR TOUCH!!」と「テリー伊藤の愛とブログ」だったりする。久米さんも伊藤さんも既存テレビ業界の偉大なクリエイターだ。ネットテレビでも涼しい顔でプロのお仕事をなさっているが、このお二人に頼っているようじゃ、正直Gyaoの将来は正直暗いのではないか。何で還暦前後のオヤジさんたちなの? 赤字で番組予算が無いのなら20歳代の無名で有能なクリエイターを発掘して好きにやらせたほうが絶対に良いような気がする。真に時代を変えて行くのはそういう人たちだ。テレビ局を買収しようとしたり、既存のテレビ番組制作の枠組みの中で発想していたのでは、おそらく電波で済むものは済み、銅線で済むものは銅線で済んでしまうような気がしないでもない。むろん、技術的経済的に優れていれば代替化は進むだろう。しかし、代替はしょせん代替に過ぎない。IT革命って代替化のことだったのかいな? まあ、既存テレビと同じ手法を取るのもひとつの方法ではあるし、実際、Gyaoで大手スポンサーのCMが増えれば既存民放にとっては脅威なのかもしれない。しかし、メディアの覇権ってのは印刷機と聖書がセットであったように、その特性を生かし他のメディアを凌駕するような新しいコンテンツを創造して初めて握れるものなのだ。伝送路の変更だけなら電話工事屋さんに任せればよい。よって伝送路の品質を上げたNTTさんには金は払う。でも、我家ではテレビや電話はもう間に合っている。伝送路が良くなったからって、今以上にテレビを見るわけでもないし電話もかけない。セットで押し売りされても買わないものは買わないよ。「トリプルプレイ」で享受できる魅力的なコンテンツって一体何なのよ? 推進応援する人々は具体像を早急に示して欲しい。さてさて「自分に出来ないようなこと」を偉そうに吠えてるだけなので、そろそろお終いにするが、最後に気になったことをひとつ。「トリプルプレイ」って野球では守備側が首尾良くあっと云う間に3つアウトを取る「三併殺」のことだったよな。あれ?IT業界っていつから守備側に回ってしまったんだろ? それともこれは既存メディアの守備でトリプルプレイが成立し、IT業界の攻撃終了って意味かいな?
ダタより安いものもある
![]() Visual Studio 2005 Express Edition(日本語版)が無償公開されている。VBが無料なんて一昔前では考えられないようなことだが、現実となった。プログラマーのVB6からVB.NETへの移行が思ったように進まず、シェアが他のネットワーク言語に奪われている現状をMSは何とかしたかったのだろう。NETに移行しないVB6プログラマーが増えてしまった表向きの理由は、VB6とNETは基本的に別物で資産の完全移行が難しい点が挙げられるが、案外、ネットによるユーザー認証が導入され違法運用が出来なくなったことの方が理由として大きいのではないか? VisualStudio2003をセット価格は12万円程。VB.NET2003を単体で購入しても2万円程度はする。「ちょっと遊んでみたい」とか「できるかどうかわからんが勉強してみたい」と思った程度の人が手を出せる価格ではない。実際、かつてはさらに高価だったはずだが、多くの人々は学校や社用のソフトを個人のパソコンにインストールしてVBを学び、ある者は挫折しある者は病みつきになり、結果、VBのシェアを増やしていたようにも思う。もちろん違法なことは絶対によろしくないが、個人ユーザーなんてそんなものなのだ。それらが厳しく禁止された昨今、一方でJavaの開発環境が無償公開されてたり、オープンソースなプログラミング言語もある。これじゃ初心者やホビーユーザーがVBから離れていくわな~。今回の対応は必然だったのかも知れない。Expressとはいえ1.5GBものインストール領域が必要な完全版。サポートがないだけでとりあえず何でも出来る。VBだけでなくC#やC++やJavaも、"Visual Web Developer 2005 Express Edition"なんてのも無償。開発言語は使う人の能力次第で対価を生むシロモノだ。人によってはタダより安くなる場合もあるだろう。元来、MSはダタの方が儲かるって商売を上手にやってきた会社で、これもその一環と云えなくもない。世間にはダタより高いものはないと云う戒めの言葉もあるが、とりあえず私は金もスキルも無いが貧乏人、世界一の金持ちに感謝してせいぜい利用させてもらおうと思う。
Visual Studio 2005 Express Edition(日本語版)が無償公開されている。VBが無料なんて一昔前では考えられないようなことだが、現実となった。プログラマーのVB6からVB.NETへの移行が思ったように進まず、シェアが他のネットワーク言語に奪われている現状をMSは何とかしたかったのだろう。NETに移行しないVB6プログラマーが増えてしまった表向きの理由は、VB6とNETは基本的に別物で資産の完全移行が難しい点が挙げられるが、案外、ネットによるユーザー認証が導入され違法運用が出来なくなったことの方が理由として大きいのではないか? VisualStudio2003をセット価格は12万円程。VB.NET2003を単体で購入しても2万円程度はする。「ちょっと遊んでみたい」とか「できるかどうかわからんが勉強してみたい」と思った程度の人が手を出せる価格ではない。実際、かつてはさらに高価だったはずだが、多くの人々は学校や社用のソフトを個人のパソコンにインストールしてVBを学び、ある者は挫折しある者は病みつきになり、結果、VBのシェアを増やしていたようにも思う。もちろん違法なことは絶対によろしくないが、個人ユーザーなんてそんなものなのだ。それらが厳しく禁止された昨今、一方でJavaの開発環境が無償公開されてたり、オープンソースなプログラミング言語もある。これじゃ初心者やホビーユーザーがVBから離れていくわな~。今回の対応は必然だったのかも知れない。Expressとはいえ1.5GBものインストール領域が必要な完全版。サポートがないだけでとりあえず何でも出来る。VBだけでなくC#やC++やJavaも、"Visual Web Developer 2005 Express Edition"なんてのも無償。開発言語は使う人の能力次第で対価を生むシロモノだ。人によってはタダより安くなる場合もあるだろう。元来、MSはダタの方が儲かるって商売を上手にやってきた会社で、これもその一環と云えなくもない。世間にはダタより高いものはないと云う戒めの言葉もあるが、とりあえず私は金もスキルも無いが貧乏人、世界一の金持ちに感謝してせいぜい利用させてもらおうと思う。
超安物本格的ヘッドホン
 ■密閉型ステレオヘッドホン
■密閉型ステレオヘッドホン
■EH-V115 (EXCELSOUND)
■¥800(ドンキホーテ)
密閉型のヘッドホンが800円だぞ、オイ。左右独立ボリュームコントロールが安っぽいぞ、オイ。中国あたりで作っていそうな如何にもバッタなデザインだぞ、オイ。でも、音がイイぞ。何故かイイぞ。800円なら絶対買いだぞ。オイ。ってな訳で、耳をすっぽり覆ってしまうタイプの昔ながらの密閉型ヘッドホンの超安物を紹介。安っぽいゆえに超軽量。だから長時間装着していても重くない。インナーイヤー型のように耳穴が痛くならないし、オープンイヤー型のように耳や耳たぶも圧迫することもない。予想外に快適だ。ダイナミックレンジは一応、20Hz-20kHz。シンプルな構造ゆえにスピーカの反応速度が速く、乾いた低音が心地よい。ヘッドホンアンプで使うような本格的オーディオヘッドホンとは比べるべくもないが、インターネットラジオを聴きながらパソコン作業をするような向きにはオススメ。実はこのヘッドホン、35年も前からカートリッジやトーンアームなどのオーディオアクセサリーを作ってきた日本の会社の製品。価格を下げるため海外で作っているようだが、音に対する最低限の礼儀は忘れていないって感じが伝わってきておおいに好感を持った。もうひとつ買いにいこっと...。(笑)
大森林に向かって立つ
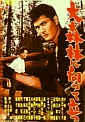 大森林に向かって立つ 1961年 カラー 84分 日活
大森林に向かって立つ 1961年 カラー 84分 日活
■監督:野村孝
■出演:小林旭/浅丘ルリ子/かまやつヒロシ
この頃のプログラムピクチャーは大量に生産されていたためか、タイトルが類型化していたり大袈裟なものが少なくない。大森林に向かって立ってどうするんだ? ・・・とも思うが、これは山林を舞台にした小林旭のアクション映画。同年公開の「散弾銃の男」(監督:鈴木清順、主演:二谷英明)は飛騨、木曽方面でのロケ、こちらは伊那が舞台だ。映画の随所に伊那周辺の1961年風景が現れる。冒頭、労務者を載せ浅丘ルリ子が運転するトラックは、旧伊那市役所の前を北から南に通過し、伊那大橋をなぜか高遠方面から伊那市内に向けて渡り、美和ダムの上を走って進んでいく。上映数分で伊那市民は大満足?? 美和ダムは映画公開の2年前1959年に竣工した多目的ダム。この三峰川(みぶがわ)総合開発事業ではその後いろいろなことがあったが、とりあえず当時は地元自慢の施設だったようだ。続く森林のシーンは太田切渓谷での撮影。このあたりには中央アルプスの山々から天竜川に注ぐ急峻な支流がいくつかあり、その渓谷はそれぞれ大田切、与田切など「〇〇切」と呼ばれている。「〇〇切」は登ればどこも大森林だ。途中で登場する見事な夕景は、千畳敷から南アルプス方面を見た朝焼けに似ている。が撮影場所は不明。ちなみに駒ケ岳ロープウェーなどまだ出来ていない。小林旭や労務者たちが繰り出す夜の街は錦町あたりのようだ。「酒は仙醸」なる電柱看板も見える。酒場で歌うは当然、小林旭。しかし注目はギターを持ち彼とデュエットする若者だ。なんとそれは「短髪の」かまやつひろし、驚け! 驚くと云えば100人以上のエキストラが櫓を囲んで勘太郎踊りを踊るシーンもあるが、ロケ場所が地元民でない私には不明。小林旭が歩く傍らにはなぜか「つばめタクシー」なるわざとらしい看板も登場、地元では著名なタクシー会社だ。きっとロケ移動の便宜を図ったのだろう。櫓の場所は駅前あたりと思われるが、朝焼け同様もう少し調べないと正確なことはわからない。さてこの時期の映画でヒーローヒロインが語らうシーンと云えばなぜか街が一望出来る高台ってのがお決まりのパターンだったりするが、この映画にもそれはある。春日城址だ。桜の名所。全国的には高遠城址の桜の方が圧倒的に有名だがシーズン中は観光客でいっぱい、そのため、地元民のお花見はこの春日城址らしい。そして、浅丘ルリ子が融資を受けに訪れる銀行は、そのものズバリ、八十二銀行伊那支店!! 浅丘ルリ子の父が療養している場所は伊那からやや離れた蓼科。広大な八ヶ岳から蓼科山方面にゆっくりとパンニングする映像が見られるが道路は未舗装だ。当然ビーナスラインはない。最後に今回最大のサプライズ(?)。それは後半部で蓼科に向かった浅丘ルリ子を小林旭がジープで追いかけるシーンに隠れていた。ジープは冒頭でも登場した伊那大橋を今度は伊那(入舟)側から高遠(中央)側に渡るのだが、ボンネットに乗せたカメラが、運転する小林旭を撮ればその背景に当然町並みも映る。それをコマ送りでツブサに見るとロケ見物の野次馬が数十人みなこちらを見ているのがよく判る。まあそれはご愛嬌として、橋のたもとにある食堂の看板に私は驚いた。「飯島食堂」。知る人ぞ知る伊那の名所?(笑)。4人以上で一緒に食べると昼からサービス満点の中華定食。蓋から具が溢れるほどのボリウムたっぷりのソースカツ丼は、駒ヶ根が名物として売る出すずっと以前からから地元の人々に親しまれていた。(「中華料理 飯島」で Google検索すればと地元の方のBlogでその写真が閲覧可能だ。驚け!)「研ナオコさん元気ですか?」などと誰にもわからんオチもつけておこう。(^_^) 最近の伊那市はあちらこちらの地方都市と同様、中心市街地の空洞化が進み夜の街の勢いはサッパリだが、その伊那市もかつては人口あたりの飲み屋の数が全国3位と云われた時期もあったらしい。戦前戦後は映画「伊那の勘太郎」が大ヒットし有名となった街でもある。この映画に映る伊那の街はその往時の賑わい留めているのが嬉しい。
コピーワンスな衛星放送受信機
![]() スカパーのコピーワンス信号はもうずいぶん前から付加されているものなので、いわゆる大手メーカーの発売するチューナーならばどれもそれに対応しているものと思っていたが実際はそうでもないらしい。真面目にコピーワンス信号を吐いているのはスカパーがチューナーレンタルにも採用している韓国製のH*MAXだけのようだ。大手家電量販店の中にはパラボラ付で通常1万円以上するH*MAXチューナーを5千円で販売し、スカパーの新規入会購入5千円キャッシュバックで特典で事実上0円!などと宣伝している店もある。レンタル機に採用されているだけあって番組表や予約設定などではスカパーとの親和性が高く、見るだけとか録画は1回だけでOKという人であれば特に支障はないので、それで良いなら0円という価格は大きな魅力だろう。しかし、この製品、DVD-Rなどへの録画目的でスカパーに加入している人の場合は、タダでも選ばない方が賢明だ。なぜなら、このチューナーを使うとほとんどのスカパープログラムで「2次コピー」が不可能となってしまうからだ。HDDへ1回、あるいはDVDに直接1回までは録画可能だが、そこから他のDVDメディアへのデジタルコピーは出来ない。つまり、HDDに留守録画した番組をDVD-Rなどのメディアに移せないない訳で、映像コレクターさん達にとっては全くオハナシにならない仕様なのだ。例外的にDVD-RAMと+RWの場合は、録画番組のHDDからDVDメディアへのコピーならぬ「移動」が可能だが、そこからさらにパソコンや他のDVDメディアへのコピーは出来ない。(コピーしたところで画像は真っ黒、音も出ない。)DVD-RAMに対応したプレーヤーなんてのも限られているし、+RWも再生はともかく録画可能なレコーダーはあまり見ない。それに-R、-RW、+Rが使えないのでは何かと不便だ。汎用性があるとはとてもいえない。ところがなぜか、なぜかそんなH*MAXと異なり、日本の大手ブランドチューナーは、2005年10月の時点で未だにそのコピーワンス信号を吐かないのだ。受け側の大手メーカー製DVDレコーダーの方は例外なくCPDMを検知する仕様になっているというのに、送り側の大手メーカー製チューナーの方は全く対応していないのだから面白い。放送波にコピーワンス信号が含まれていてもチューナーがコピーワンス信号を吐かなければ、2次コピーは可能となる。ファイナライズすれば他の機器でも使用可能だ。ついでにバラしてしまうとDVD-RAMの場合はファイナライズさえも不要・・・VRモードそのまんまのファイルをPCドライブで参照可能なので、VR_MOVIE.VROという単体のMPEG2ストリームファイルの拡張子をmpgに変更すればパソコン上で編集するなりオーサリングするなりまったくの自由となる。さらに老婆心ながら付け加えておくと、スカパーの放送波にはデジタル部分でコピーワンス信号が付加されている他、アナログ部分にはマクロビジョンプロテクトが施されている。アナログ出力で再キャプチャするなど、RCAピンコードやS端子ケーブルで信号渡しする場合にはそれ相応の(笑)対応が必要だ。こうしたことは実際に映像を扱う上ではとても重要なことで、その可不可の差は大きい問題であるハズなのだが、コピーワンスのH*MAXとコピーフリーな世界の**NYのチューナーの店頭での価格差はたった3~4千円だった。この価格差ならば、どちらを選ぶかは自明の理だろう。韓国製が法遵守で日本製が「???」ってのも笑えるが、それが実態のようだ。
スカパーのコピーワンス信号はもうずいぶん前から付加されているものなので、いわゆる大手メーカーの発売するチューナーならばどれもそれに対応しているものと思っていたが実際はそうでもないらしい。真面目にコピーワンス信号を吐いているのはスカパーがチューナーレンタルにも採用している韓国製のH*MAXだけのようだ。大手家電量販店の中にはパラボラ付で通常1万円以上するH*MAXチューナーを5千円で販売し、スカパーの新規入会購入5千円キャッシュバックで特典で事実上0円!などと宣伝している店もある。レンタル機に採用されているだけあって番組表や予約設定などではスカパーとの親和性が高く、見るだけとか録画は1回だけでOKという人であれば特に支障はないので、それで良いなら0円という価格は大きな魅力だろう。しかし、この製品、DVD-Rなどへの録画目的でスカパーに加入している人の場合は、タダでも選ばない方が賢明だ。なぜなら、このチューナーを使うとほとんどのスカパープログラムで「2次コピー」が不可能となってしまうからだ。HDDへ1回、あるいはDVDに直接1回までは録画可能だが、そこから他のDVDメディアへのデジタルコピーは出来ない。つまり、HDDに留守録画した番組をDVD-Rなどのメディアに移せないない訳で、映像コレクターさん達にとっては全くオハナシにならない仕様なのだ。例外的にDVD-RAMと+RWの場合は、録画番組のHDDからDVDメディアへのコピーならぬ「移動」が可能だが、そこからさらにパソコンや他のDVDメディアへのコピーは出来ない。(コピーしたところで画像は真っ黒、音も出ない。)DVD-RAMに対応したプレーヤーなんてのも限られているし、+RWも再生はともかく録画可能なレコーダーはあまり見ない。それに-R、-RW、+Rが使えないのでは何かと不便だ。汎用性があるとはとてもいえない。ところがなぜか、なぜかそんなH*MAXと異なり、日本の大手ブランドチューナーは、2005年10月の時点で未だにそのコピーワンス信号を吐かないのだ。受け側の大手メーカー製DVDレコーダーの方は例外なくCPDMを検知する仕様になっているというのに、送り側の大手メーカー製チューナーの方は全く対応していないのだから面白い。放送波にコピーワンス信号が含まれていてもチューナーがコピーワンス信号を吐かなければ、2次コピーは可能となる。ファイナライズすれば他の機器でも使用可能だ。ついでにバラしてしまうとDVD-RAMの場合はファイナライズさえも不要・・・VRモードそのまんまのファイルをPCドライブで参照可能なので、VR_MOVIE.VROという単体のMPEG2ストリームファイルの拡張子をmpgに変更すればパソコン上で編集するなりオーサリングするなりまったくの自由となる。さらに老婆心ながら付け加えておくと、スカパーの放送波にはデジタル部分でコピーワンス信号が付加されている他、アナログ部分にはマクロビジョンプロテクトが施されている。アナログ出力で再キャプチャするなど、RCAピンコードやS端子ケーブルで信号渡しする場合にはそれ相応の(笑)対応が必要だ。こうしたことは実際に映像を扱う上ではとても重要なことで、その可不可の差は大きい問題であるハズなのだが、コピーワンスのH*MAXとコピーフリーな世界の**NYのチューナーの店頭での価格差はたった3~4千円だった。この価格差ならば、どちらを選ぶかは自明の理だろう。韓国製が法遵守で日本製が「???」ってのも笑えるが、それが実態のようだ。
理想国家の現実
 米南部を襲ったハリケーン「カトリーナ」が見せてくれたもの。それは私達が理想とする国の貧しさだ。台風の被害は日本にもある。たびたび巨大地震の被害にも遭っている。被災地はどこも悲惨なもの。しかし、日本の被災地であのような情けない貧富の格差を見せ付けられることがあるだろうか。米国ではそのうち大統領の号令と共に、軍だ警察だ民間だなどとカッコイイ救援隊が現地に駆けつけて英雄的な救助活動を開始し、全米の中産階級の子息達は賛美歌を唄いながら被災地のための募金活動をすることになるのだろう。しかしそれらがいくら美しくてもニュースビデオに映った米国の現実を消し去ることは出来ない。昨今、日本はその米国を手本に努力した者が報われる社会にしようと構造改革の真っ只中。国や経済界のトップから末端のサラリーマンに至るまで「貧富の格差がないのは正しい能力評価がなされていない証拠。よって悪。」と思い込んでいる。さらに大多数の日本人は、自分は大学も出てるいる、会社では一定の地位もある、努力もしている、だから当然中流層に残れる・・・と勘違いをしているらしい。なんともおめでたい。自由競争社会とはとどのつまり、その中流層の選別なのだ。中流層の努力の成果がそのまま中流層に還元されると思ったら大間違い。それはたぶん社民主義と云われているもの。皆様が選択したがっている自由主義社会では、元中流層が生みだす資本は上流層に搾取されることになる。そして上流層はさらに超え太る。確かに国家経済事体は強くなるだろう。しかし、涙ぐましい努力を続けた僅かばかりの者達が中流層に残れる一方、それまで自分は中流層と思っていただった大多数の者達は貧困層に転落することになる。アメリカンドリームで成り上がった成功者ばかりを見ていたら騙されるよん。貧困層が増えれば当然治安は悪化。日本の場合、過酷で悲惨と云われた阪神大震災や中越地震の際も一部例外は除き治安は確保されていた。それこそ中流層の互助意識によってこそ為せるものなのだが、その中流層がやせ細ってしまえば貧困層を助ける能力はない。ひとたび災害が発生すれば略奪強姦殺人のオンパレードだ。貧者の多くは他人のことなと構っていられない。これが世界一豊かな国の現実。そんな国になりたいとアメリカンスタイルな政治家や政党に一票を投ずる君。20年後には「国肥えてあなたその日暮らし」だよん。よ~く考えよう。
米南部を襲ったハリケーン「カトリーナ」が見せてくれたもの。それは私達が理想とする国の貧しさだ。台風の被害は日本にもある。たびたび巨大地震の被害にも遭っている。被災地はどこも悲惨なもの。しかし、日本の被災地であのような情けない貧富の格差を見せ付けられることがあるだろうか。米国ではそのうち大統領の号令と共に、軍だ警察だ民間だなどとカッコイイ救援隊が現地に駆けつけて英雄的な救助活動を開始し、全米の中産階級の子息達は賛美歌を唄いながら被災地のための募金活動をすることになるのだろう。しかしそれらがいくら美しくてもニュースビデオに映った米国の現実を消し去ることは出来ない。昨今、日本はその米国を手本に努力した者が報われる社会にしようと構造改革の真っ只中。国や経済界のトップから末端のサラリーマンに至るまで「貧富の格差がないのは正しい能力評価がなされていない証拠。よって悪。」と思い込んでいる。さらに大多数の日本人は、自分は大学も出てるいる、会社では一定の地位もある、努力もしている、だから当然中流層に残れる・・・と勘違いをしているらしい。なんともおめでたい。自由競争社会とはとどのつまり、その中流層の選別なのだ。中流層の努力の成果がそのまま中流層に還元されると思ったら大間違い。それはたぶん社民主義と云われているもの。皆様が選択したがっている自由主義社会では、元中流層が生みだす資本は上流層に搾取されることになる。そして上流層はさらに超え太る。確かに国家経済事体は強くなるだろう。しかし、涙ぐましい努力を続けた僅かばかりの者達が中流層に残れる一方、それまで自分は中流層と思っていただった大多数の者達は貧困層に転落することになる。アメリカンドリームで成り上がった成功者ばかりを見ていたら騙されるよん。貧困層が増えれば当然治安は悪化。日本の場合、過酷で悲惨と云われた阪神大震災や中越地震の際も一部例外は除き治安は確保されていた。それこそ中流層の互助意識によってこそ為せるものなのだが、その中流層がやせ細ってしまえば貧困層を助ける能力はない。ひとたび災害が発生すれば略奪強姦殺人のオンパレードだ。貧者の多くは他人のことなと構っていられない。これが世界一豊かな国の現実。そんな国になりたいとアメリカンスタイルな政治家や政党に一票を投ずる君。20年後には「国肥えてあなたその日暮らし」だよん。よ~く考えよう。
箱の中の街
![]() 地方での生活で最もグローバリズムを感じる場所、それはジャ※コだ。私の家はある地方都市の郊外にある。近くには江戸時代からある街道が通り、かつてそこには商店街があった。八百屋、肉屋、菓子屋、荒物屋、蕎麦屋、煙草屋、下駄屋、布団屋、風呂屋、床屋、桶屋、電気屋などが軒を並べ、やや離れたところには米屋、魚屋、寿司屋、書店、薬局、麩屋、写真屋、時計眼鏡店などもあった。各店は奉仕券なる共通のサービスチケットを発行し、それを集めると行ける温泉旅行が地域の人々の楽しみだった。そこに30年ほど前、県下初のジャ※コが進出した。するとほどなく商店街は壊滅した。今でも菓子屋、下駄屋など数軒が細々と残るが、マトモな商売をしているのは床屋くらいだ。旧商店街経営者の中には自殺者も出たという。そして今度はなんとそのジャ※コが消えるらしい。さらに郊外、高速道路のインターチェンジに近い場所に巨大なショッピングセンターとなって移転するとの情報がある。昨年から今年にかけて私は近県にあるその会社の巨大ショッピングモール2箇所(群馬県太田市と富山県高岡市)を実際に訪れてみたが、それは店というより巨大な箱の中に詰まった街だった。箱の中には120を超えるテナントが入り、さらにレストラン街やシネコンまでもがある。ジャ※コはその巨大なモールの中心となるキーテナントに過ぎない。無料駐車場の収容能力は4000台。毎日曜日この駐車場がいっぱいになるようなことになれば、今度は地域の商店街ではなく駅前の中心商店街も壊滅することになるだろう。経済原理主義の立場に立ち、地球規模での効率化、競争力強化を考えれば、とりあえずこの現象は「進歩」だ。事実、全国規模で展開するレストランやファストフード店のメニューはコストパフォーマンスは異常に高い。人件費も極端に節制されているようで、その価格展開たるやとても個人商店に真似できるものではない。貧乏人の私にとっては安いということはとりあえず有難いことではある。しかし、高速道路を使い200kmもクルマを飛ばして訪ねた大規模ショッピングモールではあったが、私の場合は特にそこで購入したいと思うようなモノは何ひとつ無かった。家人は家の近くでは売られてないブランドがあったと衣料を数点購入したようだが、私には何の魅力も無かった。結局、私は家人と一緒に昼飯を食っただけで、あとは同じ敷地内にある日帰り温泉施設で寝ていた。120もの店が並んでいるがとりたてて珍しいものがあるわけではない。要は広い意味での生活用品がごまんと置いてあるだけだ。観光施設ではないから地元名産品があるわけでもない。要するにこの手のショッピングセンターの中身はどこも同じなのだ。まさにグローバリズム。これがわが町に出来れば当然利用はするだろう。そこに行けば生活に必要な品は何でも手に入る。200円ほどのガソリン代はかかるもののとりあえず便利だ。しかし、このBLOGを見れば判るとおり、無駄なことをしたり無駄な時間を過ごすのが好きな私にとって、便利なだけが有り難い訳でもない。日本中何処に行っても同じ箱同じ店だなんてのはむしろツマラナイことだと言ってもいい。店によって様子が違っていたら時には隣町のショッピングセンターにも行きたくなるような気もするが、どこも同じならわざわざ行く気にもなれない。20年程前、何処の町の駅前もミニ東京化しツマラナクなったと云われた時期があった。それでも田舎の町には訳のワカラン怪しい店が表通り裏通りにあり、恐る恐るそれを利用するのが旅のスリルだった。その頃は自分の街と同じ店を見つけると親近感を覚え逆に喜んだりしたものだ。昨今そんな楽しみは消失した。地方都市の駅前はどこも衰退し、歩く気にもならない街になり、クルマで郊外に行ってみれば自分の住む町と同じ全国一律のチェーン店が並び、明らかに旅はつまらなくなってしまった。かつては文化的に近しい同じ県内でも他の町に行くと風情が変わり、その微妙な差が案外面白かったのに今はそんな感慨はほとんど皆無だ。一体これは進歩なのだろうかそれとも衰退なのだろうか。まあ、巨大ショッピングモールが出来て、首都東京にある商品が総て手に入るなら、ある意味それは「進歩」だろう。しかし、巨大ショッピングモールに実際に並ぶ商品を眺めていると、仮に我が町に巨大ショッピングモールが出来たところで、マニアアライクで珍しい商品が欲しければ、新幹線に乗ってTYOに行くしかないのは明白。その程度のもので地域文化や町並みが破壊されるなら、それは進歩でなく明らかに「後退」だ。日本中の地域コミニュティを破壊し尽した箱型商店街の創業者の息子がなんと野党第一党の党首として政権をめざしているんじゃ、この流れはそう簡単に変わるまい。淋しい国になったものだ。最近、グローカリズム(Glocalism)なる言葉が流行り始めている。これは"Globalism"と"Localism"の合成語のようだが、「地球的規模の発想で地域活動を行う」という考え方らしい。反グローバル主義とはやや趣が異なる。グローバルに考えることは重要だが地域性を失ってはいけないということかなとも思う。実際、グローバリズムが単に東京化米国化を意味するならそれは人類にとって巨大な文化的損失になるだろうことは私のような馬鹿でも判る。仮に各地域の多様な文化を吸い上げて優れたものだけを還元するのがグローバリズムだとしたらローカルの衰退はやがて世界の衰退を招くだろう。いくら優れていても均質化単純化された社会から生まれる文化など長い眼で見れば明らかに不毛だからだ。経済的には無駄と思えることも文化的には意味のあることはいくらでもある。私の街に出来る大規模ショッピングセンターも、せめて建物を仏閣型にするくらいの洒落は欲しいと思う。だから何だと云えばそれまでだが、その無駄が大切なのだ。そういう発想を誰もしなくなったところに今日の不毛がある。
地方での生活で最もグローバリズムを感じる場所、それはジャ※コだ。私の家はある地方都市の郊外にある。近くには江戸時代からある街道が通り、かつてそこには商店街があった。八百屋、肉屋、菓子屋、荒物屋、蕎麦屋、煙草屋、下駄屋、布団屋、風呂屋、床屋、桶屋、電気屋などが軒を並べ、やや離れたところには米屋、魚屋、寿司屋、書店、薬局、麩屋、写真屋、時計眼鏡店などもあった。各店は奉仕券なる共通のサービスチケットを発行し、それを集めると行ける温泉旅行が地域の人々の楽しみだった。そこに30年ほど前、県下初のジャ※コが進出した。するとほどなく商店街は壊滅した。今でも菓子屋、下駄屋など数軒が細々と残るが、マトモな商売をしているのは床屋くらいだ。旧商店街経営者の中には自殺者も出たという。そして今度はなんとそのジャ※コが消えるらしい。さらに郊外、高速道路のインターチェンジに近い場所に巨大なショッピングセンターとなって移転するとの情報がある。昨年から今年にかけて私は近県にあるその会社の巨大ショッピングモール2箇所(群馬県太田市と富山県高岡市)を実際に訪れてみたが、それは店というより巨大な箱の中に詰まった街だった。箱の中には120を超えるテナントが入り、さらにレストラン街やシネコンまでもがある。ジャ※コはその巨大なモールの中心となるキーテナントに過ぎない。無料駐車場の収容能力は4000台。毎日曜日この駐車場がいっぱいになるようなことになれば、今度は地域の商店街ではなく駅前の中心商店街も壊滅することになるだろう。経済原理主義の立場に立ち、地球規模での効率化、競争力強化を考えれば、とりあえずこの現象は「進歩」だ。事実、全国規模で展開するレストランやファストフード店のメニューはコストパフォーマンスは異常に高い。人件費も極端に節制されているようで、その価格展開たるやとても個人商店に真似できるものではない。貧乏人の私にとっては安いということはとりあえず有難いことではある。しかし、高速道路を使い200kmもクルマを飛ばして訪ねた大規模ショッピングモールではあったが、私の場合は特にそこで購入したいと思うようなモノは何ひとつ無かった。家人は家の近くでは売られてないブランドがあったと衣料を数点購入したようだが、私には何の魅力も無かった。結局、私は家人と一緒に昼飯を食っただけで、あとは同じ敷地内にある日帰り温泉施設で寝ていた。120もの店が並んでいるがとりたてて珍しいものがあるわけではない。要は広い意味での生活用品がごまんと置いてあるだけだ。観光施設ではないから地元名産品があるわけでもない。要するにこの手のショッピングセンターの中身はどこも同じなのだ。まさにグローバリズム。これがわが町に出来れば当然利用はするだろう。そこに行けば生活に必要な品は何でも手に入る。200円ほどのガソリン代はかかるもののとりあえず便利だ。しかし、このBLOGを見れば判るとおり、無駄なことをしたり無駄な時間を過ごすのが好きな私にとって、便利なだけが有り難い訳でもない。日本中何処に行っても同じ箱同じ店だなんてのはむしろツマラナイことだと言ってもいい。店によって様子が違っていたら時には隣町のショッピングセンターにも行きたくなるような気もするが、どこも同じならわざわざ行く気にもなれない。20年程前、何処の町の駅前もミニ東京化しツマラナクなったと云われた時期があった。それでも田舎の町には訳のワカラン怪しい店が表通り裏通りにあり、恐る恐るそれを利用するのが旅のスリルだった。その頃は自分の街と同じ店を見つけると親近感を覚え逆に喜んだりしたものだ。昨今そんな楽しみは消失した。地方都市の駅前はどこも衰退し、歩く気にもならない街になり、クルマで郊外に行ってみれば自分の住む町と同じ全国一律のチェーン店が並び、明らかに旅はつまらなくなってしまった。かつては文化的に近しい同じ県内でも他の町に行くと風情が変わり、その微妙な差が案外面白かったのに今はそんな感慨はほとんど皆無だ。一体これは進歩なのだろうかそれとも衰退なのだろうか。まあ、巨大ショッピングモールが出来て、首都東京にある商品が総て手に入るなら、ある意味それは「進歩」だろう。しかし、巨大ショッピングモールに実際に並ぶ商品を眺めていると、仮に我が町に巨大ショッピングモールが出来たところで、マニアアライクで珍しい商品が欲しければ、新幹線に乗ってTYOに行くしかないのは明白。その程度のもので地域文化や町並みが破壊されるなら、それは進歩でなく明らかに「後退」だ。日本中の地域コミニュティを破壊し尽した箱型商店街の創業者の息子がなんと野党第一党の党首として政権をめざしているんじゃ、この流れはそう簡単に変わるまい。淋しい国になったものだ。最近、グローカリズム(Glocalism)なる言葉が流行り始めている。これは"Globalism"と"Localism"の合成語のようだが、「地球的規模の発想で地域活動を行う」という考え方らしい。反グローバル主義とはやや趣が異なる。グローバルに考えることは重要だが地域性を失ってはいけないということかなとも思う。実際、グローバリズムが単に東京化米国化を意味するならそれは人類にとって巨大な文化的損失になるだろうことは私のような馬鹿でも判る。仮に各地域の多様な文化を吸い上げて優れたものだけを還元するのがグローバリズムだとしたらローカルの衰退はやがて世界の衰退を招くだろう。いくら優れていても均質化単純化された社会から生まれる文化など長い眼で見れば明らかに不毛だからだ。経済的には無駄と思えることも文化的には意味のあることはいくらでもある。私の街に出来る大規模ショッピングセンターも、せめて建物を仏閣型にするくらいの洒落は欲しいと思う。だから何だと云えばそれまでだが、その無駄が大切なのだ。そういう発想を誰もしなくなったところに今日の不毛がある。
管弦楽フォーク
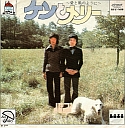 いまどきこのジャケットデザインに反応するのはクルマ好きのオヤジだけかな? 私は音楽が好きで聴いている。この頃のフォークソングはこの曲のように生のストリングス(弦楽編曲)が使われていることが多い。ロックバンドに管弦楽という編成は音に清潔感があって爽快だ。これを知的な音などというとクラシックコンプレックスが丸出しになってしまうが、まあそんなところだ。戦後のポップス歌謡曲は進駐軍キャンプ周辺でジャズを演奏していた人々を中心に発展してきたので、伴奏は金管が主役のジャズのピッグバンドが当たり前だった。「原信夫とシャープス&フラッツ」「岡本章生とゲイスターズ」「ダン池田とニューブリード」とかね。ところが60年代の後半になるとビッグバンド編成でない歌謡曲が増えてくる。これはとりあえずビートルズの影響と言い切ってしまっていいだろう。ビートルズブームでポピュラーソング伴奏の主役の座が完全にジャズからロックに移っただけはなく、弦楽四重奏をバックにしたイエスタディなど、それまでに無かった楽器編成で次々にヒットを飛ばしたものだから、豪華なはずのピッグバンド伴奏がダサく聴こえるようになってしまった。ボブディランがロックバンドを従えて唄うようになったのもその頃だ。「ケン&メリー~愛と風のように~(BUZZ)1972」も歌自体はギター1本で唄うようなフォークソングだが、若き日の高橋幸宏によるアクセントの効いたドラムと大袈裟なスリングスによってソフトロックの名曲に変貌している。日本ではこのパターンのキーパーソンはきっと村井邦彦氏だろう。ヒューマンルネサンス「廃墟の鳩(タイガース)1968」、再評価が待たれる「愛の理由(トワ・エ・モワ)1969」に始まり、誰でも知ってる「翼をください(赤い鳥)1971」、隠れた名曲「憶えているかい(ガロ)1973」など、かなり早い段階で欧米で流行し始めた編曲手法を導入している。これにはマルチトラックレコーディングが可能になったという技術的な進歩も背景に含まれる。アメリカのA&Mレーヴェル、ヨーロッパ(フランス)ではポールモーリアが管弦楽器をパート録音し、それまでのレコードでは聴くことが出来なかった抜けの良いキラキラストリングスの音が世に溢れたのだ。70年代に入ると加藤和彦がすぐに反応し「あの素晴らしい愛をもう一度(加藤和彦と北山修)1971」を出せば、新人バンド、チューリップも青木望編曲の「夏色のおもいで(チューリップ)1973」や「青春の影(チューリップ)1974」などで大胆な管弦楽編曲を取り入れている。こうしたアレンジは60年代的の発想の集大成として70年代前半にほぼ手法が完成した。そういう意味ではプログレッシブロックと同根だと私は勝手に考えている。プログレが70年代中期に失速したのと同じように、この管弦楽フォークも「翳りゆく部屋(荒井由実)1976」あたりを最後に流行のメインストリームから離れていく。プログレが編み出したマルチキーボードシステムがオケの代用品となり、5人編成程度のロックバンドをバックに唄う歌謡歌手が増えてしまったのだから皮肉なものだ。その後の時代と云えば、村井邦彦氏のアルファレコードの最初のアルバム、厚見玲衣によるシンフォニックプログレバンド「ムーンダンサー(ムーンダンサー)1979」あたりが印象深いが、ディスコ全盛だった当時の流行からはかなり逸れた音だ。ほどなくアルファはYMOや戸川純で時代の寵児となるが、それは生弦が鳴るような音楽ではなかった。また、同じ時期で弦が美しい曲といえば「ローレライ(H2O)1980」がある。彼ら珠玉のデビュー曲。「想い出がいっぱい(H2O)1983」が大ヒットするが、弦が活躍するのはそのあたりまで。以後、彼らは当時の音楽的流行に翻弄されながらの苦闘する。彼らが60年代的なるものの日本での最期の音だったのかも知れない。
いまどきこのジャケットデザインに反応するのはクルマ好きのオヤジだけかな? 私は音楽が好きで聴いている。この頃のフォークソングはこの曲のように生のストリングス(弦楽編曲)が使われていることが多い。ロックバンドに管弦楽という編成は音に清潔感があって爽快だ。これを知的な音などというとクラシックコンプレックスが丸出しになってしまうが、まあそんなところだ。戦後のポップス歌謡曲は進駐軍キャンプ周辺でジャズを演奏していた人々を中心に発展してきたので、伴奏は金管が主役のジャズのピッグバンドが当たり前だった。「原信夫とシャープス&フラッツ」「岡本章生とゲイスターズ」「ダン池田とニューブリード」とかね。ところが60年代の後半になるとビッグバンド編成でない歌謡曲が増えてくる。これはとりあえずビートルズの影響と言い切ってしまっていいだろう。ビートルズブームでポピュラーソング伴奏の主役の座が完全にジャズからロックに移っただけはなく、弦楽四重奏をバックにしたイエスタディなど、それまでに無かった楽器編成で次々にヒットを飛ばしたものだから、豪華なはずのピッグバンド伴奏がダサく聴こえるようになってしまった。ボブディランがロックバンドを従えて唄うようになったのもその頃だ。「ケン&メリー~愛と風のように~(BUZZ)1972」も歌自体はギター1本で唄うようなフォークソングだが、若き日の高橋幸宏によるアクセントの効いたドラムと大袈裟なスリングスによってソフトロックの名曲に変貌している。日本ではこのパターンのキーパーソンはきっと村井邦彦氏だろう。ヒューマンルネサンス「廃墟の鳩(タイガース)1968」、再評価が待たれる「愛の理由(トワ・エ・モワ)1969」に始まり、誰でも知ってる「翼をください(赤い鳥)1971」、隠れた名曲「憶えているかい(ガロ)1973」など、かなり早い段階で欧米で流行し始めた編曲手法を導入している。これにはマルチトラックレコーディングが可能になったという技術的な進歩も背景に含まれる。アメリカのA&Mレーヴェル、ヨーロッパ(フランス)ではポールモーリアが管弦楽器をパート録音し、それまでのレコードでは聴くことが出来なかった抜けの良いキラキラストリングスの音が世に溢れたのだ。70年代に入ると加藤和彦がすぐに反応し「あの素晴らしい愛をもう一度(加藤和彦と北山修)1971」を出せば、新人バンド、チューリップも青木望編曲の「夏色のおもいで(チューリップ)1973」や「青春の影(チューリップ)1974」などで大胆な管弦楽編曲を取り入れている。こうしたアレンジは60年代的の発想の集大成として70年代前半にほぼ手法が完成した。そういう意味ではプログレッシブロックと同根だと私は勝手に考えている。プログレが70年代中期に失速したのと同じように、この管弦楽フォークも「翳りゆく部屋(荒井由実)1976」あたりを最後に流行のメインストリームから離れていく。プログレが編み出したマルチキーボードシステムがオケの代用品となり、5人編成程度のロックバンドをバックに唄う歌謡歌手が増えてしまったのだから皮肉なものだ。その後の時代と云えば、村井邦彦氏のアルファレコードの最初のアルバム、厚見玲衣によるシンフォニックプログレバンド「ムーンダンサー(ムーンダンサー)1979」あたりが印象深いが、ディスコ全盛だった当時の流行からはかなり逸れた音だ。ほどなくアルファはYMOや戸川純で時代の寵児となるが、それは生弦が鳴るような音楽ではなかった。また、同じ時期で弦が美しい曲といえば「ローレライ(H2O)1980」がある。彼ら珠玉のデビュー曲。「想い出がいっぱい(H2O)1983」が大ヒットするが、弦が活躍するのはそのあたりまで。以後、彼らは当時の音楽的流行に翻弄されながらの苦闘する。彼らが60年代的なるものの日本での最期の音だったのかも知れない。
日本民営化の行方
改革なくして成長なし」これが日本の常識になって久しい。国の借金が730兆円もあるのだ。何らか改革をしなければいずれ断末魔の叫びを聞くことになるのだろう。・・・と思うようになってからもずいぶん経つ。2000年頃の気分では、今頃はもう私のように仕事のできないダメなサラリーマンは失業し、僅かな銀行預金は紙切れ同然となり、一杯のかけそばを家族4人で有難く食うような生活をしている予定だった。あれから5年、小泉構造改革は掛け声はともかく実質的には一向に進んでいないのだが、とりあえず低所得者層の我家でも蕎麦屋に行けば大盛りそばやら冷やしたぬそばなどをひとり一品づつそれぞれ好きなものを未だにたらふく食べさせてもらっている。まったく有り難いことだ。天皇陛下に感謝しなければいけない。さて、進まぬ構造改革といえば郵政民営化法案も抵抗勢力の反対にあい廃案となってしまった。小泉首相のマジ切れぶりに、このまま行ったら2010年代には「かけそば暮らし」になるだろうと心配する人々は喝采し、綿貫さんや亀井チャンが右往左往しているのを楽しんでいるようにも見える。もっと品が無い連中は今まで身分が安定し潰れる心配のない職場で働いていた郵政公務員(現在は公社職員)の皆さんが人並みの世間の辛さを味わって苦労するのではないかと喜んでいる。まったくイヤな世の中だ。ところで、そんな政治のドタバタをよそに日本の景気がなぜかこのところ踊り場を脱し始めているのが面白い。銀行の不良債権処理が進み、民間のリストラも一段落した。それでもやっぱり2010年代には「かけそば暮らし」が待っているのだろうか?日本の国家予算は年間約80兆。借金が730兆ってことは、年収800万のサラリーマンが7千万の借金を背負ってるのと同じ。個人だったら正に樹海逝き。尋常ではない。なのにどうして破綻しないのか。とりあえずそれは借金主の立場が強いから。国という借金主はいざとなれば借金を踏み倒したり、通貨そのものの価値を変えて借金を誤魔化したりもできる。だから個人の借金ほどの危機感はなく、むしろある程度の借金ならば、あった方が景気が良くなるという側面すらある。破綻しない理由はもうひとつある。これは庶民より実は金持ちの味方である大手メディアがあまり報じない常識のひとつなのだが、それは日本国の借金の貸主のほとんどは日本人だってこと。これは大きい。だから諸外国も日本経済に元気がないと儲け話が少なくなるから「はよ構造改革をして元気になってネ!」ぐらいのことしか云わない。しかしこれが仮に国の借金の貸主が外資だったとしたらどうだろう。大騒ぎだ。当然の如くIMFが介入し、今頃日本はかつてのブラジルやアルゼンチンの如く火達磨になっていたことだろう。ところが貸主も借主も日本人じゃ財政は破綻しても国は滅びない。それどころか貸主が日本人でそれも我々とは違い銀行にたんまりと金品を預けている富裕層の皆様とくれば日本政府もペイオフやら新円発行などなかなか出来ない。そんなことしたらお金持ちの皆さんが大損害を被ってしまう。それでいながら貧乏人も含め公平に広く痛みをわかちあえる消費税率アップの方はOKってんだから案外日本の政治も判り易い。ところが日本人は戦前から政府のいうことは素直に聞く国民性。日本の借金が増えたのは我々庶民が真面目に働かなったからと思い込み、痛みに耐え、「殺されても構わない」と不退転の決意で突き進む男小泉純一郎を支持してやまないのだから、美しい。これぞ日本繁栄の原点だ。いっそのこと昨今の現状は天皇陛下に申し訳ないから消費税率を50%程度にでもするか。そうすりゃ税収が年間50兆ほど増えるから10数年で借金が返せるわい。・・・などという馬鹿げた話はともかくとして、実はその国の借金、貸主さんの中に渦中の郵便局さんがいるのをご存知だろうか。借主じゃあない「貸主」だ。で、その額なんと140兆。もちろんその原資は国民から集めた郵便貯金やら保険なのだが、とりあえず140兆も金を貸しているんだから優良企業なのではないか。そんな会社どこにもない。もちろん言われている簡保施設に無駄と不正が多いのは正す必要はあるが、実は郵便事業そのものは黒字だったりもするのだ。首相からは民営化してもやっていけるとのお墨付も頂いている。おいおいそんな美味しい公社を一般企業するのは勿体無くはないか。国の機関をスリム化して経費削減するのは結構だが、民営化したとたんに外資に巣食われたんじゃ目も当てられないよな。黒猫大和と競争してるようじゃ世界じゃとても戦えない。案外ドイツポストあたりに骨抜きにされるんじゃないか。改革=民営化だと思ったら大間違いだ。当たり前のことだが民営化とは自由競争の荒波に揉まれるということ。ダメな会社は潰れて当然とか言ってる場合ではない。そこに外資が絡んだらとんでもない悲劇が日本を襲うことになる。