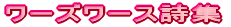 (3)
(3)| ホークスヘッドからウィンダミア湖を見る。手前の町がホークスヘッド。 |
|---|
 |
ワーズワースは、グラマースクール在学中、父親の死という第二の悲劇に見舞われました。13歳のクリスマス休暇中のことです。そのときを思い起こして書いた詩を、少々長いのですが次に紹介します。その後の彼にとっての原風景とも言える光景がここに歌われています。
| One Christmas-time, On the glad eve of its dear holidays, Feverish, and tired, and restless, I went forth Into the fields, impatient for the sight Of those led palfreys that should bear us home, My brothers and myself. There rose a crag, That, from the meeting-point of two highways Ascending, overlooked them both, far stretched ; Thither, uncertain on which road to fix My expectation, thither I repaired, Scout-like, and gained the summit ; 'twas a day Tempestuous, dark, and wild, and on the grass I sate half-sheltered by a naked wall ; Upon my right hand couched a single sheep, Upon my left a blasted hawthorn stood ; With those companions at my side, I watched, Straining my eyes intensely, as the mist Gave intermitting prospect of the copse And plain beneath. Ere we to school returned, That dreary time, ere we had been ten days Sojourners in my father's house, he died ; And I and my three brothers, orphans then, Followed his body to the grave. The event, With all the sorrow that it brought, appeared A chastisement; and when I called to mind That day so lately past, when from the crag I looked in such anxiety of hope ; With trite reflections of morality, Yet in the deepest passion, I bowed low To God, Who thus corrected my desires ; And, afterwards, the wind and sleety rain, And all the business of the elements, The single sheep, and the one blasted tree, And the bleak music from that old stone wall, The noise of wood and water, and the mist That on the line of each of those two roads Advanced in such indisputable shapes ; All these were kindred spectacles and sounds To which I oft repaired, and thence would drink, As at a fountain ; and on winter nights, Down to this very time, when storm and rain Beat on my roof, or, haply, at noon-day, While in a grove 1 walk, whose lofty trees, Laden with summer's thickest foliage, rock In a strong wind, some working of the spirit, Some inward agitations thence are brought, Whate'er their office, whether to beguile Thoughts over busy in the course they took, Or animate an hour of vacant ease. |
これについても、つたない私の訳を記しておきます。
| クリスマス休暇を前にしたある日、 迎えにくるはずの馬車が待ちきれなくて、 私は原っぱの方にまっしぐらに駆けていった。 村にやってくる二本の道が交わるあたりに岩山があり、 そこからどちらの道も遠くまで見渡された。 馬車はどちらから来るのだろう。 斥候のような気分で進んでいき、岩山を登った。 その日は風がひゅーひゅーと吹き荒れていた。 私は吹きさらしの石壁に身を寄せ、草の上にしゃがみ込んだ。 見ると右手に羊が一匹うずくまっており、 左手には冬枯れの山査子が一本さびしく立っていた。 霧が出てきた。眼下の林や野原は今にも視界から消えそうになった。 私はひたすら目をこらし、馬車の姿を追い求めた。 帰省して十日も経たない、打ち萎れた季節に、父が死んだ。 私は兄と二人の弟とともに、父の遺体を野辺に送った。 深い悲しみのうちにことは進んでいき、 すべてが私にはむごい懲罰に思えた。 そして、あの日のことが思い出されてきた。 岩山の上で期待に胸を震わせていたあの日のことが。 あのときのはやる気持ちを思い起こすと、 通り一遍の道徳的反省などでなく、 もっと奥深いところの感情がこみ上げてきて、 私は思わず神に頭を垂れた。 神は私に、希望や欲望の何とはかなく虚しいものであるかを教え諭した。 成長した後にも、 あの日の風雨のさすまじさ、自然の威力、 一匹の羊、冬枯れの木、 石壁を打つ寂寥とした風の音、 森や水辺のざわめき、 二本の道を進んでくる霧のありありとした姿、 これらすべてが一つの光景、一つの響きに結ばれて、 何度も何度も私はそこに立ち返り、 泉のようにその水を飲むのだった。 冬の夜、激しい風雨が屋根を打ちすえるとき、 夏の日盛りの森で、 生いしげる大木を見上げるとき、 風に打たれる巨岩を目にするとき、 私の心には決まってある働き、内面の震えが訪れるのだ。 それがいかなる意味を持とうとも、 日々の煩わしさを避けるためだけのものであったとしても、 むなしい安逸のひとときに一瞬の生気を吹き込むだけのものであったとしても…。 |
こうして彼ら兄弟は、最年長のリチャードが15歳、次男のウィリアムはまだ13歳という年端もいかぬ少年期に、早くも両親を二人とも失ってしまったのでした。その上、父親が遺言を残さなかったことによる金銭トラブルにすら巻き込まれることになりました(ここでは言及しませんが)。
ウィリアムにとっては、母親の死はまだ8歳のとき。悲しみもさほど深刻ではなかったでしょうが、父親の死による衝撃は計り知れないものでした。クリスマス休暇で迎えの馬車を待っているときの荒涼とした牧草地の風景が、引き続く父親の死という衝撃によって彼にとっては生涯忘れられない記憶となり、その後も、折に触れて脳裏によみがえる深層部の原風景となったのです。上の詩はそのことを物語っています。
なお、父親の死後も彼らはそれぞれ、卒業までホークスヘッドにとどまりました。『序曲』の中でワーズワースは、
"… as a schoolboy an afterwards, I lodged for nearly the space of ten years."
と述べています。厳密に言えば、9歳から17歳まで、8年間のアンおばさんとのつきあいでした。彼にとっておばさんは「下宿のおかみさん」などという通り一遍の言葉で表現できるものではなく、まさに母親そのものでした。
ワーズワースはホークスヘッド時代、校長先生から詩人としての才能を高く見込まれ、自らも、将来進むべき道を「詩人」だとはっきり自覚するようになっていました。
その頃の彼の作品のうち、父親の死の翌年(14歳のとき)に書いた詩をひとつ紹介します。
| Noble Sandys, inspir'd with great design, Reared Hawkshead's happy roof, and call'd it mine. There have I loved to show the tender age The golden precepts of the classic page; To lead the mind to those Elysian plains Where, throned in gold, immortal Science reigns; Fair to the view is sacred Truth display'd, In all the majesty of light array'd, To teach, on rapid wings, the curious soul To roam from heaven to heaven, from pole to pole, From thence to search the mystic cause of things And follow Nature to her secret springs. |
自信はないのですが、私の訳を記しておきます。
| サンディズ師が偉大な使命感に燃え、 私立学校として創設したホークスヘッド・グラマースクール。 私はこの学校をこよなく愛する。 そこで子供たちは古典的金言に触れ、 その精神は理想郷へと導かれる。 永遠の科学の御代に王冠を授ける理想郷、 出し物は、荘厳な灯明に照らし出された 神聖な真実。 そこでは、好奇に燃える心が、駿馬の翼に乗って 天空を自在に駆けめぐりつつ、 物事の神秘の根源を探り、 自然の秘密の泉に導かれる。 |
| Edwin Sandys |
|---|
 |
なお、彼の生家は今も残っていて、いまだに現役の農家なのだそうです。500年も昔の家がいまだに現役の農家だなんて、日本ではとても考えられないことです。これが石積み文化に支えられたイギリスのキャパシティーなのかと、素人なりに納得してしまいます。とてつもない保温力です。ワーズワースの生家が二百数十年前とちっとも変わらぬ姿を残していることなど、驚くにも値しないわけですね。
上の詩は、少年ワーズワースの生き生きとした学びの日々を彷彿させる、力強い詩だと思います。同時に、彼のような俊才の向学心をも十分に満たしてくれるホークスヘッド・グラマースクールのすばらしい教育内容と教授力も、この詩から読み取れます。
グラマースクールを卒業したワーズワースは、ケンブリッジ大学に入学し、さらに大学卒業後は、語学の勉強のためにフランスに渡りました。そこでフランス革命に遭遇し、また、ある女性との間に娘を一人もうけることともなりました(後に、イギリスでの正式な結婚を前に、妹ドロシーとともに再度渡仏し、娘にも会い、しかるべき後処理はしたようです)。
イギリスに戻った後の1795年、後見人の叔父から父親の遺産をもらい受け、詩と文学に没頭できる経済的なゆとりを得ました。同じ95年には詩人としての生涯を決定づけるコールリッジとの出会いがあり、1797年、コールリッジと2人で最初の詩集『抒情詩集』(Lyrical Ballads)を出版しました。ところが、詩集の評判を見ぬうちに、ワーズワースもコールリッジもそれぞれ別々にドイツ旅行に出かけ、ワーズワースは1799年になってようやくグラスミア湖のほとりに一軒の家を借りて定住生活に入りました。ドロシーと2人で住んだその家を「ダブ・コテージ」と名付け、そこでの約10年間が、ワーズワースの創作活動の最も充実した時期となりました。
| ダブコテージ(ワーズワースよりやや後) 家の前を羊の群れが通っている。 |
ダブコテージ(現在) 今も、家の姿は昔のまま。 |
|---|---|
 |
 |
その頃の彼らの生活ぶりは、ドロシーの日記や手紙に生き生きと描かれています。そこで次は、ドロシーの日記と手紙の章に移ることにします。
