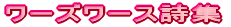 (1)
(1)
ワーズワース(1770〜1850)は湖水地方に生まれ、生涯の大半を湖水地方で過ごしました。外に出ていたのは、10代後半から20代前半にかけての学びの期間、つまり、ケンブリッジ大学時代とそれに続くフランス、ドイツ旅行の間だけです。
湖水地方に戻ってからは、妹ドロシーや親友のコールリッジらとともに、山や湖、牧草地、小さな町々を散策するのを日課としました。信じられないことですが、彼らは何十キロという距離をすら平気で歩きました。月明かりがあれば、夜をすら苦にせず歩きました。
『湖水案内』(Guide to the Lakes)は、そうした日々の散策を土台とした、湖水地方の総合ガイドブックです。ほとんどあらゆる観光スポットについて、地誌、歴史、見どころ、行き方、主要な町からの距離、その地に関わった人物などを詳細に記しています。
もちろん散策の主要な目的は詩作でした。詩を書くための題材探しとインスピレーションの獲得、つまり創作に対する絶えざる情熱が、ワーズワースの頭を離れることはありませんでした。中でも、代表作のほとんどを書いたとされる20代後半から30代にかけての10数年間は、生活全体が詩とともにありました。散策によってインスピレーションを得、帰宅後それを作品に仕上げ、さらにドロシーやコールリッジに読んで聞かせる。これが毎日の日課であり、大きな楽しみでした。
彼らは日のあるかぎり、月明かりのあるかぎり、自然の中を歩き回り、人を訪ね、詩を作り、朗読し、読書し、本について語り合いました。これが彼ら知的青年の楽しみのすべてでした。ゲームやテレビといった受動的娯楽のない時代の一日は、今に比べると何と充実して長かったことでしょう(こうした彼らの日々の生活ぶりをありありと再現してくれるのは、ドロシーの日記です)。
私がワーズワースに深い親しみを覚えるようになったきっかけは、自伝的長編叙事詩 『序曲』(The Prelude)でした。
今回のイギリス旅行では、『序曲』に描かれた情景のいくつかを自分の目と足で確かめたいという思いが強くありました。もちろん200年前と今とでは、同じ湖水地方とは言え、様子は違っているでしょう。『序曲』に描かれているひなびた渡し場がそのまま今もひなびた渡し場であるはずはなく、行ってみると賑々しいヨットハーバーになっていた。そういうこともありました。しかし、建物や自然は私の想像をはるかに越えるレベルで、過去がそのまま今につながっていました。
建物がいつまでも残る。これが木の文化に対する石積み文化の決定的な特性なのだとつくづく実感しました。家も塀も牧場の柵もすべて石積みです(スレート状の薄い石を積み重ねたもの)。これは200年やそこらのオーダーで変化するものではなさそうです。自然風化の時間だけ保つのです。

一軒の家にお茶に招かれたのですが、その家は17世紀に建てられ、18世紀に一部増築され、それ以降は手を加えていないとのことでした。300年以上も使い続けている家ということになります。日本ではこういう民家はほとんど見られませんが、英国では決して珍しいことではなく、ごく当たり前の光景です。
『序曲』から、私が気に入っている詩をいくつか紹介します。素人の私がワーズワースを紹介するなどとはあまりにおこがましいのですが、その大胆さもあながち許されないことではないというお墨付きのような文章を、最近読んだバートランド・ラッセルのエッセイに見つけたので、ことのついでに、まずそれを載せておきます。
「History as an art」というエッセイ(正確には講演記録)からの一文です。
見当違いな読み取り方をしているのかもしれませんが、おそらく次のような意味です。
Clearly the kind of history which is to contribute to the mental life of those who are not historians must have certain qualities that more professional work need not have, and, conversely , does not require certain thigs which one would look for in a learned monograph.
一人の人の精神を強く震わせた事柄は、その内容の如何に関わらず、すでに個人の枠を越えて普遍性に向かう価値を内在させている。これはよく考えてみれば、あらゆる芸術の成立基盤そのものです。
ある人の精神に強く影響を与えた歴史的事柄は、その人がもし歴史の素人であったとしても、専門的考証や先行論文の確認などという厳密な作業を抜きにして、その意味や価値はすでに語られる資格をもっている。
精神の震えを語ることができるのはその人を擱いて他にないわけだから、その人は語る資格を持つのです。事実の客観性や、先人の言及などをすべて調べてからでないと語る資格がない、というものではないのです。
というわけで、まず、少年ワーズワースが夏休みを終えて学校があるホークスヘッド(Hawkshead)に戻ってくる場面から始めます。
私なりに訳しますと、
Bright was the summer's noon when quickening steps
Followed each other till a dreary moor
Was crossed, a bare ridge clomb, upon whose top
Standing alone, as from a rampart's edge,
I overlooked the bed of Windermere,
Like a vast river, stretching in the sun.
With exultation, at my feet I saw
Lake, islands, promontories, gleaming bays,
A universe of Nature's fairest forms
Proudly revealed with instantaneous burst,
Magnificent, and beautiful, and gay.
I bounded down the hill shouting amain
For the old Ferryman ; to the shout the rocks
Replied, and when the Charon of the flood
Had staid his oars, and touched the jutting pier,
I did not step into the well-known boat
Without a cordial greeting. Thence with speed
Up the familiar hill I took my way
Towards that sweet Valley where I had been reared ;
'Twas but a short hour's walk, ere veering round
I saw the snow-white church upon her hill
Sit like a throned Lady, sending out
A gracious look all over her domain.
Yon azure smoke betrays the lurking town ;
With eager footsteps I advance and reach
The cottage threshold where my journey closed.
Glad welcome had I, with some tears, perhaps,
From my old Dame, so kind and motherly,
While she perused me with a parent's pride.
夏の日の盛り、
足どり軽くヒースの野を越え、
牧場の丘を登り、
高みに一人立つと、まるで城壁に立ったように、
眼下にウインダミア湖が姿を現し、
大河に似たその水面が、太陽に輝いている。
歓び躍る心で、私は
湖を、島々を、岬を、照り輝く入り江を、
それら自然のもろもろの形象が、
一瞬の光景の中に融合して、誇らしげに、
荘厳で、麗美で、華やかな姿を現出するさまを、
足下に眺めた。
私は丘を駆け下りながら、力一杯、
渡し守のおじいさんに声をかけた。
その声は岩にこだまし、
三途の川を渡ろうとしていたおじいさんは、
櫂を止め、渡し場に舟を戻した。
顔見知りのおじいさんにお礼を言って舟に乗ると、
舟は早や対岸に着き、私は丘を駆け上がり、
甘い香りのホークスヘッドへと向かう。
そこは私が育ったところ。
少し歩けばもう、道が曲がりきらないうちに、
丘の上に白い教会が見えてきた。
女王様のように、
慈悲深いまなざしを投げかけてくれる教会。
町は青くたなびく煙の奥にひそんでいるが、
はやる足どりは軽く、
たちまち私は家の入り口に着いた。
うっすら涙を浮かべたおばさんが、
迎えてくれる。
おばさんは本当のお母さんのように優しく、
誇らしげに私を見つめる。
| ウインダミア湖の渡し船 (ワーズワース時代) |
|---|
 |
なお、この詩に生き生きと描かれている自分は、子供時代の自分ではなく、ケンブリッジの学生だった頃、夏休みにホークスヘッドを再訪したときの自分だというのが正しいようにも思えるのですが(今回の旅行で入手した R.J.Hutchings の説)、ここでは最初に私が『序曲』を読んだときの印象のまま、子供時代の一場面だと解釈しておきます。日本の高木市之助も子供時代の帰省説をとっており、ワーズワース学者の E. Legouis もそうだということなので(こちらは直接は確認していないのですが)、私の解釈もあながち的外れではないと思います。
ワーズワースは『序曲』を生涯書き直し続けたため、一つの詩に中においても、詩人の立つ時間的視点が微妙にずれている箇所があります。この詩もそうで、それが解釈のずれを生んでいるように思います。
