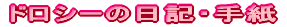 (2)
(2)ドロシーの日記には物乞い(beggar)の話がよく出てきます。19世紀初頭のイギリスではそのような光景は珍しくなかったようです。住む家がなく、放浪の旅をする家族、これが物乞いの実態です。社会的な背景は私にはわかりませんが、ワーズワース兄妹のような有閑青年がいる反面、その日をしのぐために物乞いをしないといけない人たちもいたということになります。
そんな日記の一つを紹介します。物語性もあり、庶民の暮らしの一端を知る手がかりともなって、なかなか興味深いです。
 |
 |
| ダブ・コテージからライダル、アンブルサイド方面に向かう道。ワーズワース兄妹や弟のジョンが毎日のように歩いた道です。 | |
| June 1800, Tuesday 10th. A cold, yet sunshiny morning. John carried letters to Ambleside. Wm. stuck peas. After dinner he lay down. John not at home. I stuck peas alone. Cold showers with hail and rain, but at half-past five, after a heavy rain, the lake became calm and very beautiful. Those parts of the water which were perfectly unruffled lay like green islands of various shapes. William and I walked to Ambleside to seek lodgings for C. No letters. No papers. It was a very cold cheerless evening. John had been fishing in Langdale and was gone to bed. On Tuesday, May 27th, a very tall woman, tall much beyond the measure of tall women, called at the door. She had on a very long brown cloak and a very white cap, without bonnet. Her face was excessively brown, but it had plainly once been fair. She led a little bare-footed child about two years old by the hand, and said her husband, who was a tinker, was gone before with the other children. I gave her a piece of bread. Afterwards on my way to Ambleside, beside the bridge at Rydale, I saw her husband sitting by the roadside, his two asses feeding beside him, and the two young children at play upon the grass. The man did not beg. 1 passed on and about a quarter of a mile further I saw two boys before me, one about 10, the other about 8 years old, at play chasing a butterfly. They were wild figures, not very ragged, but without shoes and stockings. The hat of the elder was wreathed round with yellow flowers, the younger whose hat was only a rimless crown, had stuck it round with laurel leaves. They continued at play till I drew very near, and then they addressed me with the begging cant and the whining voice of sorrow. I said " I served your mother this morning," (The boys were so like the woman who had called at the door that I could not be mistaken.) "O!" says the elder, "you could not serve my mother for she's dead, and my father's on at the next town he's a potter." I persisted in my assertion, and that I would give them nothing. Says the elder, " Let's away," and away they flew like lightning. They had however sauntered so long in their road that they did not reach Ambleside before me, and I saw them go up to Matthew Harrison's house with their wallet upon the elder's shoulder, and creeping with a beggar's complaining foot. On my return through Ambleside I met in the street the mother driving her asses, in the two panniers of one of which were the two little children, whom she was chiding and threatening with a wand which she used to drive on her asses, while the little things hung in wantonness over the pannier's edge. The woman had told me in the morning that she was of Scotland, which her accent fully proved, but that she had lived (I think at Wigtoun), that they could not keep a house and so they travelled. |
| 1800年7月10日(火) 朝、寒いが日は照っている。ジョンはアンブルサイドに手紙を出しに行った。ウィリアムは豆に支えの棒を差している。昼食後、ウィリアムは横になった。ジョンはまだ帰ってこない。私は一人で豆に棒を差した。 雹の混じった冷たい雨が降る。5時半ごろようやく上がった。湖は静けさを取り戻し、鮮やかな景色が出現した。波がすっかり治まったところが、湖上に浮かぶ緑の島々のようだ。 私はウィリアムとアンブルサイドに出かけ、コールリッジのために家を探した。手紙は来ていない。新聞もない。寒くて陰気な夕べ。ジョンはラングデールで釣りをしていたらしい。もう寝に行った。 そうそう、2週間前にこんなことがあった。並外れて背の高い女の人が玄関先に物乞いにきた。長い茶色の外套を着、日よけのない白い帽子をかぶった女性だった。顔は薄黒く日焼けしていたが、かつて美人だったことは一目でわかった。2歳くらいの小さな素足の子供の手を引いていた。夫は鋳掛け屋をしていたが、子供たちを連れて出て行ってしまったのだと言っていた。私はパンを一切れあげた。 それからしばらくしてアンブルサイドに行くために出かけると、ライダルの橋のたもとで彼女の夫らしき人を見かけた。道ばたに腰を下ろし、そばに二匹のロバがいて草を食べていた。二人の幼子が草の上で遊んでいた。物乞いをする風はなかった。 通り過ぎて数百メートル行ったとき、前方に二人の男の子の姿が見えた。10歳と8歳くらいの子で、蝶を追っかけて遊んでいた。だらしない恰好をしているが、決してぼろを着ているわけではなかった。ただ、靴も靴下も履いていなかった。上の子は帽子を黄色い花で飾っていた。下の子は縁なしの山形帽の周囲に月桂樹の葉を刺していた。 二人は夢中になって遊んでいたが、私がすぐそばまで近づくと、突然哀れっぽい調子で物乞いをした。「あなたたちのお母さんには今朝、施し物をしましたよ」と言うと、「えっ?」と上の子が驚き、「そんなはずないよ。母ちゃんはもう死んじゃったもの。父ちゃんは隣町で焼き物作りをしてんだけどね」と言った。私の目には、この二人は玄関で物乞いをしたあの女性そっくりだった。間違うはずはなかった。私は、「絶対間違いはないんだから」と言い張って、子供たちには何も施しをしなかった。すると突然、「逃げるぞ」と上の子が叫び、二人は稲妻のように駆け出していった。 しかし、姿を消したあとはまた長い道中をぶらぶらしていたようで、アンブルサイドまで行かないうちに再び彼らを見かけた。二人はマシュー・ハリソンさんの家に行こうとしていた。上の子は肩にずだ袋を担ぎ、わざと辛そうに足を引きずっていた。 アンブルサイドからの帰り道、今度はロバを追い立てながら歩いている母親を見かけた。二つある荷カゴのうちの一つには小さな子供が二人入っていた。母親は、ロバを追い立てる杖を振り上げながら、子供たちを叱りつけていた。荷カゴの端からは何か小さな物がぶら下がって揺れていた。 彼女は朝、スコットランドの出身だと言っていた。訛りからもそれはわかった。ウイッグタウンに住んでいたようだが、家を維持することができなくなって旅に出たらしい。 |
アンブルサイドはウインダミア湖の北岸にある美しい町です。南北に長いウインダミア湖の西岸地方(ホースクヘッドの町もその一つ)に陸伝いに行くには必ずアンブルサイドを通らないといけない。そんな交通の要所です。グラスミア湖畔にあるダブ・コテージからは、グラスミア湖、ライダル湖を横に見ながら南に約1時間(5キロほど)でアンブルサイドに着きます。ワーズワース兄妹にとってはほんの腹ごなし程度の散歩コースです。
| アンブルサイドの町 | アンブルサイドにある橋の上の家 |
|---|---|
 |
 |
ダブ・コテージに落ち着いた彼らが今度はコールリッジのためにアンブルサイドで家探しをしていたことが、この記事からわかります。最終的にはコールリッジはアンブルサイドではなくケジック(ダブ・コテージから北西に約20キロ)に家を借りることになります。
グラスミアからアンブルサイドまでの5キロほどの道中を、10歳を頭に4、5人の子供を持つ親子が物乞いをしながら旅していたわけです。しかも、一緒にではなくバラバラに。大きな荷物はロバの背中に乗せ、おそらく野宿をしながらの旅だったのでしょう。父親は物乞いには加わらず、もっぱら母親と上2人の子供が物乞い役だったようです。
悲しい光景ですが、ある意味ではこれは一般庶民の旅の常態だったのではないでしょうか。今日なら旅は楽しいレジャーですが、昔は人生の辛さを象徴する出来事だったはずです。経済的余裕のある人ならともかく、余裕をなくしたからこそ旅に出ざるをえない人にとっては、道中をしのぐ手段は物乞い以外に考えられません。「旅人イコール物乞い」、そんな図式化も決して大げさではない状況が200年前までの当たり前の姿だった気がします。
だからこそ、ドロシーの日記に物乞いの話が頻繁に出てくるのでしょう。ドロシーやウィリアムは家の中で過ごすタイプではなく、一日の大半を戸外で過ごす人でしたから、よけいに旅人(すなわち物乞い)に出くわす機会が多かったと思われます。
10歳と8歳の子供が蝶を追いかけて遊んでいたこと。帽子を花や月桂樹で飾っていたこと。これを読むと、まっすぐで無邪気な子供心と、彼らを育てた親のきちんとした生活習慣が感じられてほっとします。
子供が裸足なのは、今日的な目で見れば尋常ではないのですが、たとえば『大草原の小さな家』を書いたアメリカのローラ・インガルスなども、子供時代は戸外でも裸足が常でした。この日記から半世紀以上も後の1870年代のことです。舗装された道を裸足で歩くのはつらいけれど、草の道を歩くのなら裸足はかえって心地よいものです(とローラ・インガルスが書いています)。当時の道はたいていが草の道でした。
●ダンスパーティーのこと
ダブ・コテージでは子供たちのダンスパーティーも開かれていました。今度はその記事を紹介します。
| 26' December 1805 I have been summoned into the kitchen to dance with Johnny and have danced till I am out of Breath. According to annual custom, our Grasmere Fiddler is going his rounds, and all the children of the neighbouring houses are assembled in the kitchen to dance. Johnny has long talked of the time when the Fiddler was to come; but he was too shy to dance with any Body but me, and though he exhibited very boldly when I was down stairs, I find they cannot persuade him to stir again. It is a pleasant sound they make with their little pattering feet upon the stone floor, half a dozen of them, Boys and Girls; Dorothy is in ecstasy, and John looks as grave as an old Man. |
| 1805年12月26日 私は呼び出されてジョニーと台所で踊った。息が切れるまで踊り続けた。毎年のことだが、グラスミアのバイオリン弾きがこの日、家々を流して回る。それで、私の家の近所では、子供たちがみんな我が家の台所に集まってきて踊ることになっている。ジョニーはかなり前から、いつバイオリン弾きが来るの?と、そればかり尋ねていた。そのくせ彼は恥ずかしがり屋で、私以外の誰とも踊ろうとしない。私が階下にいるときには元気な顔をしているのに、私がいなくなると、もう誰も彼を動かすことさえできない。 それにしても、子供たちが小さな足で石の床を踏みならす音は気持ちいいものだ。男の子や女の子たちが5、6人集まっている。ドロシーは夢中になって踊っている。ジョン(ジョニー)はまるで老人のようにしかめっ面。 |
 |
| ダンスパーティーが開かれたダブ・コテージのキッチン。石の床です。右奥の据えつけテーブルはウィリアムの食台だったとのこと。 |
ここに出てくるジョニーとドロシーは、ウィリアムの息子と娘です。書いているドロシーからすれば甥と姪です。上の子のジョニーはなかなか気むずかしい性格のようです。それに比べると下の子のドロシーはいかにも子供らしく、その場を楽しんで踊っています。
今は音楽は好きなときにどこででも聞けますが、録音という技術のなかった昔は、音楽は生でしか聞けないものでした。考えてみると、この違いは大変なものです。家に楽器があって、それを弾く人がいる場合は別として、一般の家庭では音楽を楽しむ機会がほとんどなかったことになります。年に一度のこの日が、しかめっ面のジョニーにとってすら、実は待ち遠しくてたまらない日であったわけです。バイオリンに合わせて踊る子供たちの愉快な足音が、今ここにまで響いてきそうな気がします。
●弟ジョンの遭難
ダンスパーティーの記事と順序が少し逆転しますが、同じ1805年の春、弟のジョンが船の難破によって溺死しました。日記の中にしばしば、脇役的ではありますが登場するジョンです。
ジョンの悲劇を述べた手紙を紹介します。ドロシーの繊細な感性がよく表れた文章だと思います。ジョンという人物の不思議な魅力が伝わってきます。
| Dorothy Wordsworth to Mrs. Marshall GRASMERE, March 16, 1805. It does me good to weep for him, and it does me good to find that others weep, and I bless them for it. It is with me when I write, as when I am walking out in this vale, once so full of joy; I can turn to no object that does not remind me of our loss. I see nothing that he would not have loved and enjoyed. (途中少し不明) My consolations rather come to me in gusts of feeling than are the quiet growth of my mind. I know it will not always be so. The time will come when the light of the setting sun upon these mountain tops will be as heretofore a pure joy ; not the same gladness, that can never be, but yet a joy even more tender. It will soothe me to know how happy he would have been could he have seen the same beautiful spectacle. I shall have him with me, and yet shall know that he is out of the reach of all sorrow and pain, can never mourn for us - his tender soul was awake to all our feelings - his wishes were intimately connected with our happiness. He was taken away in the freshness of his manhood ; pure he was, and innocent as a child. Never human being was more thoroughly modest, and his courage I need not speak of, it served him in the hour of trial, he was seen speaking with apparent cheerfulness to the first mate a few minutes before the ship went down ; and when nothing more could be done he said, "The will of God be done." I have no doubt that when he felt that it was out of his power to save his life, he was as calm as before, if some thought of what we should endure did not awaken a pang. Our loss is not to be measured but by those who are acquainted with the nature of our pleasures and have seen how happily we lived together those eight months that he was under our Roof. He loved solitude, and he rejoiced in society. He would wander alone amongst these hills with his fishing-rod, or led on merely by the pleasure of walking, for many hours ; or he would walk with W. or me, or both of us, and was continually pointing out with a gladness which is seldom seen but in very young people something which perhaps would have escaped our observation ; for he had so fine an eye that no distinction was unnoticed by him, and so tender a feeling that he never noticed anything in vain. Many a time has he called me out in an evening to look at the moon or stars, or a cloudy sky, or this vale in the quiet moonlight ; but the stars and moon were his chief delight. He made of them his companions when he was at Sea, and was never tired of those thoughts which the silence of the night fed in him. Then he was so happy by the fireside, any little business of the house interested him. He loved our cottage. He helped us to furnish it, and to make the garden. Trees are growing now which he planted. He stayed with us till the 29th of September 1800, having come to us about the end of January. During that time Mary Hutchinson, now Mary Wordsworth, stayed with us six weeks. John used to walk with her everywhere, and they were exceedingly attached to each other ; and so my poor sister mourns with us, not merely because we have lost one who was so dear to William and me, but from tender love to John and an intimate knowledge of him. Her hopes as well as ours were fixed on John. I can think of nothing but of our departed brother, yet I am very tranquil to-day. I honour him, and love him, and glory in his memory. |
| 1805年3月16日、グラスミアにて、マーシャル夫人へ。 私は泣くことによってようやく耐えています。他の人たちが彼のために泣くのを見ることによってもです。その人たちに祝福あれ。 今こうして書いている間も涙は止まりません。谷間を歩きながら泣き続けています、かつてはあんなにも喜びに満ちていたこの谷間なのに。見るものすべてが私に喪失感を呼び起こします。どこを見ても、彼が愛し、喜びを感じなかったものはないのです。……。私の慰めは、静かにゆるやかに呼び起こされるのではなく、激しい感情の突風とともにやってくるようです。これからもいつもそうだというわけではないでしょうが。 今ちょうど、夕日が山の頂に美しい光を投げかける時間です。その光には今までと変わらぬ純粋の喜びが満ちています。しかし、私は同じ喜びを感じることができません。できるはずがありません。だのになぜか、私の心はこれまでにもまして穏やかに静められています。もし彼がこの美しい光景をともに眺めることができたら、どんなにか彼は幸せだろう、そう思うと私の心は和らぐのです。 私の中に彼は生きています。しかし彼が、悲しみや苦痛とは無縁の世界に行ってしまったことも私は知っています。彼はもはや私たちのために泣くことはありません。私たちの感性の中に目覚めている彼の繊細な心は、ひたすら私たちの幸せを願い続けているのです。 彼は、人生の最もはつらつとした時期に召されてしまいました。純粋で、子供のように無垢な人でした。彼ほどおごることを知らない人はありませんでした。彼の勇気は、もはや語る必要もありません。最後の試練の時、彼は勇気をもって行動しました。船が沈むわずか前、わざと明るい表情を浮かべて一等航海士と会話していた姿が目撃されています。そして、いよいよ打つべき手段がなくなったとき、最後に彼は「神のご意志のままに」とつぶやいたそうです。自分の死が避けられないことを悟った瞬間にも、彼の心はいつもと変わらず冷静だったと私は信じています。残された私たちが受ける苦悩を思って心が痛むことがなかったとしたらの話ですが。 彼と共有した喜びがいかなるものであったかを知らない人や、彼と一つ屋根の下で過ごした8ヶ月間、私たちがいかに幸せであったかを知らない人には、私たちの喪失感の大きさは推し量れないと思います。 彼は孤独を愛し、また社交的でもありました。彼は一人で何時間も山を歩き回りました。釣り道具を持っていくこともあり、歩くことをただ楽しむだけのときもありました。ウィリアムと歩き、私と歩き、あるいは3人連れだって歩くこともありました。彼はいつも、子供にしか見つけられないさまざまなこと、大人が普段見すごしてしまう小さなことを発見しては、喜んでいました。彼の目は鋭くて、どんな小さなものをも見分けられました。また彼の感性は非常に繊細でしたから、何を見ても、それをつまらないと感じることはありませんでした。夕方彼に誘われて、一緒に月や星や雲や、月明かりに照らし出されたこの谷間を眺めたことが何度あったことでしょう。星や月を眺めることが、彼にとっての最大の喜びだったのです。海の上でも彼はそれらを友としていました。夜の静けさが紡ぎ出してくれるさまざまな想像の世界で、彼は退屈することがなかったのです。 私たちの家にいるとき、彼は暖炉のそばで幸せそうでした。どんなに小さな家事にも興味を示し、私たちの家をたいへん気に入っていました。家具を取りつけたり、庭を作ったりするのを手伝ってくれました。彼が植えた木が今大きく育っています。 彼が私たちの家にやってきたのは、引っ越して間もない1800年1月のことでした。9月29日までいました。その間にメアリー・ハッチンソン、今はメアリー・ワーズワースですが、が6週間滞在しました。ジョンはよく彼女と散歩に出かけました。二人は互いに強く心を惹かれていたのです。だからこそ彼女は私たちとともにジョンの死を嘆いているのです。ウィリアムと私が大切な人がなくしたからというだけではないのです。彼女自身、ジョンを心から愛していたし、彼のことをよく知っていたのです。彼女の心は私たちと同じく、ジョンに向けられています。私はこの世を去ってしまった弟のことを考えずにはいられません。しかし、今日は心が落ち着いています。彼をたたえ、彼を愛し、彼の思い出に心からひたっています。 |
手紙の宛先人であるマーシャル夫人(ジェイン・マーシャル)はドロシーの少女時代からの親友で、不幸せだった頃、ドロシーの心の支えになってくれた人でした。
ドロシーはおそらくこの手紙を、ダブ・コテージに近い、ジョンとの思い出に満ちた谷間で書いているのだと思います。歩く道々にも涙は乾くことがなく、いつしか足はこの谷間に向かっていました。岩に腰を下ろすと、眼下にはジョンがいた頃と変わらぬグラスミア湖の姿があり、対岸の山々はゆるやかな稜線を空に向けています。
 |
| ダブ・コテージにほど近い、グラスミア湖を望む谷。ドロシーが手紙を書いたのはこの付近だったと思われる。 |
ひとしきり泣いたあと、便せんを取り出し、悲しみを吐き出すようにジェインに語りかけ始めました。気がつくと日は西に傾きかけていて、燦然とした光が山の稜線を際だたせています。あっけにとられてこの美しい光景に見とれているうちに、ドロシーは突如深い喪失感に襲われました。しかし不思議なことに、それはたちまち平安に向けて溶けていき、そばにジョンがいて夕焼けを眺めている幸せな自分が幻覚されます。うっとりと空を見つめているジョンをそばに感じると、ドロシーの心は慰撫され、筆を置く頃にはすっかり落ち着いていました。
このジョンという人、ウィリアムやドロシーの弟ですが、何という魅力にあふれた人でしょう。繊細な感性、無垢な心。子供のままの心を持ち続けた自然人です。
ドロシーが十代後半に書いた手紙に、ジョンについて次のような一言があります。
「グラマースクール時代、ウィリアムは秀才でよく勉強したが、ジョンはあまり勉強しなかった」。さらに、「リチャード(長男)も勉強は好きではなく、クリストファー(末っ子)はウイリアムに似た秀才タイプ」と続きます。
ジョンは本で学ぶタイプではなかったようです。どっぷりと自然につかり、自然の中で成長し、やがて船乗りとして世界の海に乗り出しました。しかし、勇猛かつ粗暴な海の猛者ではなく、孤独を愛し、夜の星々を友とする船乗りでした。
人生の最後の瞬間、船員を可能な限り避難させた後、自らは海の藻屑と消えはてた様子は、おそらく、生きて帰還した船員から伝え聞いたのでしょうが、ジョンの究極の勇気と責任感を劇的に示しています。
なお、私事になりますが、実は私も星が大好きで、寝ころんで夜空を見上げていると、時の経つのを忘れます。宇宙の巨大さと美しさと不思議さに圧倒されて、思いが次から次へとわき上がってくるのです。といっても、ジョンのような子供の心はもう私にはありませんが…。
星空の魅力は永遠に尽きることがありません。
