|
|
| 2011年9月20日 |
ずいぶん長くアップデートを休んでいました。
青春期の日記の整理やら、その出版の準備やらで忙しく……。
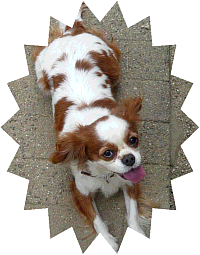 そうなんです。わが青春日記を出版しようと思い立ったのです。ほとんど半世紀もの間、手を触れることなくしまい込んでいた日記です。怖くてとても取り出す勇気がなかったものです。 そうなんです。わが青春日記を出版しようと思い立ったのです。ほとんど半世紀もの間、手を触れることなくしまい込んでいた日記です。怖くてとても取り出す勇気がなかったものです。
自分で言うのもおこがましいのですが、60年代という激動の時代を生きた一人の青年が、必死に思い悩み、人生を模索し、政治や宗教の荒波にもまれ、恋愛し、失恋し、理想と現実のはざまに苦しみ倒れ、また立ち上がり、自分というものを何度も何度も見つめ直していく日々の全過程が、わが青春日記『太平子のん太の日記』です。
京大におけるサークル活動と学生運動という特殊な環境における、特殊な一個人の日記ではあるのですが、個の特殊性を超えた、60年代の普遍的青年像がそこに描かれていると、当の本人が自分の日記を読みつつ思ったのです。
さて、どういう形で本になるのか、今のところ何の展望もありません。この記事(ブログ)を見て、ちょっと触手を動かしてくれる出版関係者がいればありがたいなと、そんな夢みたいなことを考えているぼくです。結局は自費出版だろうと、覚悟はしているのですが……。
はるか少年のころから日記を書いていたなと、ほのかな記憶はありました。しかし、それがいったいどこに始まるのか、深い海底の奥をさぐるようで、皆目見当がつかないでいました。
整理してみると、中学1年の正月が起点だとわかりました。51年前です。
とりあえず本にしようと思ったのは、中学1年の起点から大学卒業までです。その間だけでも分量は膨大で、削りに削った末、なんとか原稿用紙800枚ほどにまで絞り込みました。
さてそこで、本にしようという段になって、ぼくらのような素人の作品を一般の商業出版社が扱ってくれるはずはないと思い、やはり自費出版しかないのかなと、ちょっと悲しい気分になっています。
これまでぼくの文章が本になったのは、冊数だけならすでに2,30冊になるのですが、それらはどれも大学受験用の参考書や問題集ばかりです。短歌の同人誌はまあ別として。
今回のような本は、やはり自費出版しか手はないのでしょうか。多分そうなんでしょうね。
ともあれ、半年近くかかり切りになっていた仕事にようやく区切りがつき、今日からはふたたび、読むこと、書くことという、自分の一番の生き甲斐に向けて生活を戻していきたいと、胸おどらせている今のぼくです。
|
|
|
| 2011年9月21日 |
書斎の窓から、わが家の裏手の小さなスーパーが見下ろせる。歩いて10分ほどのところに巨大なショッピングモールがあるにもかかわらず、このスーパー、なかなかがんばっている。まるで昔の八百屋か、荒物屋か、駄菓子屋のように、地元に密着して根を張っている。
仕事に疲れると、コーヒーカップを片手に窓からぼんやり見下ろしているのだが、いつ見ても、客足が途絶えることがない。「ぽつりぽつり」という言葉がぴったりではあるが、入り口周辺の空間から人がいなくなる瞬間がないのだ。ランダムな分布ってホントにこんなのだったかなあと、数学を疑いたくなるような、間を置かぬ人の出入りである。
客の大半は、近所のおばあさん、おばさん、若奥さん、定年すぎたおじさんたち(おじいさんとは言いたくない)。休日だと若者や子どもたちもやってくる。スーパーを冷蔵庫代わりにしているらしく、日に3回も4回もやってくるおばあさんもいる。
 すぐそばに大きな県営団地があり、それに加えて、民間が開発した一戸建ての団地が周辺に広がっている。この立地のよさがスーパーの命の源なのだ。
すぐそばに大きな県営団地があり、それに加えて、民間が開発した一戸建ての団地が周辺に広がっている。この立地のよさがスーパーの命の源なのだ。
隣にはコンビニもある。どちらにも客筋はあって、ちゃんと住み分けているらしい。
わが家は両方に接していて、隣はコンビニ、裏はスーパー。便利この上ない。ひところ、夜になるとコンビニの前が不良グループのたまり場になり、周辺一同迷惑したものだが、住民の自衛的努力とパトカーの見回りによって、この夏はそれも消えた。
書斎で仕事をしていても、道路を走る車のほかに騒音らしきものが聞こえてくることはない。田園地帯と境界を接した静かな住宅地の静かなスーパー、コンビニである。この点でも、ありがたいことこの上ない。
さて、そのスーパーに先ほど若い女性がやってきた。ジーパンの足をスッスと伸ばし、「人」の形そのままの大股で歩く。そこまで足を広げなくても、と思うほど一歩が大きい。男だって、彼女にまさる歩幅で歩く人は少ないだろう。
それを見ていて、女は強くなったなとつくづく実感した。
いまのぼくは、運動といえば散歩くらいのものだが、かつては毎日ジョギングしていた。散歩をしていて思うのだが、女性のジョガーがずいぶん増えた。それも、若い二十歳代くらいの女性が増えた。わが家の周辺で見るかぎり、男と女のジョガーの比率はほとんど1:1だ。ぼくがジョギングしていた10年以上前までは、女性のジョガーに出会うことは滅多になかった。
やはり女性は強くなったのだ。
タバコを男のものと決めつけるのは偏見かもしれないけれど、ぼくの若いころは、実際、タバコは男のための嗜好物だった。女がタバコを吸っていれば、それだけで「すれた女」と見なされた。
それが今は違う。若いOLや母親が、町を歩くといたるところでタバコを吸っている。平然とくわえタバコで歩いているキャリアウーマンに出くわすこともある。女性がハンドル片手にタバコを吸っている姿も、珍しい光景ではなくなった。背景には、女性の社会進出により、女性のストレスが質・量ともに高まったことがあるのだろうか。思考様式も生活習慣も男と女の間に違いがなくなった。
かつてより相対的に増えたというよりも、いまや絶対数において女の喫煙者が男の喫煙者を上まわっているのではないかという気にすらなる。少なくとも、町で見かける喫煙者は女の方が多い。男は喫煙コーナーでひっそりわびしく吸っているのだろうか。
自販機の前で二人、三人と、若い女が地面にしゃがみ込んでタバコを吹かしているのを見たりすると(昨夜のこと)、すでに社会的な強さにおいても、男女逆転しているのかなと思ったりする。
肉体的にも、女性が男性に近づき、男性が女性に近づく傾向はたしかにあるように思う。その典型は声の高さだ。かつては「小鳥のさえずりのような声」の女性が多かったと思うのだが、最近は、男と区別がつかないような低い声でしゃべる女性が目につくようになっている。逆に、男の声は少し高くなっているようだ。声変わりしきらない若者が増えている。
若い女性の腰回り、お尻が、男のそれに近い形に変ってきたように思うのは、ぼくだけだろうか。細いスラックスがすらりと入る体型に変ってきた。ズボンをはくようになってからの意識した体型変化だと思う。スカートだけをはいていた時代には、腰の膨らみは魅力でこそあれ、見苦しくなどなかった。
細い腰は、明らかに生殖能力の低下につながるだろう。百万年後の地球に、はたして人類は生存しているのだろうか。そんな不安が頭をよぎるぼくである。
|
|
|
| 2011年9月26日 |
秋分の日に、日帰りで徳島に行ってきました。ドイツ館、香川豊彦記念館、藍の館などを見ました。
ドイツ館は、第一次世界大戦時のドイツ兵捕虜収容所跡にできた記念館です。捕虜と市民との交流は盛んだったようで、捕虜たちによる楽団が日本で初めてベートーベンの第九を演奏したことで有名です。
隣に香川豊彦記念館があります。これもなかなかいいものでした。
印象に残ったのは藍の館です。藍染めで財をなした豪商の家と仕事場が一種の博物館になっています。大きな造りの家で、買いつけに来た商人を泊めるいくつもの部屋や、贅を尽くした宴会用の大広間などをそなえています。
中でも印象に残ったのは、女中部屋でした。まるで家畜小屋か囚人部屋のような、あまりにひどい人権無視に唖然としました。玄関の脇に仕事道具などをしまうのに使ったであろう小さな土間があり、一見そこは本当に単なる土間なのですが、その天井裏にかくし部屋のような部屋があるのです。外からちょっとのぞいたくらいでは気づかない構造になっています。広さは四畳半ほど。天井が低く、かがまないと入れない。窓などなく、昼間でもうす暗い。そこが女中部屋なのです。
 |
|
藍染め豪商の家。正面より。
|
上がるための階段もないから、上り下りの際には土間から直接ハシゴをかけたのでしょう。朝早くから夜遅くまで働いて、そこは寝るだけの部屋だったと思われます。内働きの女中用です。何人いたのでしょう。少なくとも三人や四人はいたでしょう。彼女らがそこで一日の労働の疲れをいやすために雑魚寝をした。その様子が想像できます。
作業場で働く男や女も、もちろんたくさんいました。重労働に明け暮れたことが、展示されている絵で想像できます。明治期の紡績工場などと同じく、労働力を搾り取って成り立つ藍染め工業であったことがわかります。その搾取の上にできあがった藍御殿であったわけです。
途中のドライブインにカメラを置き忘れ(あとで出てきてホッとしたのですが)、写真を撮れなかったのが残念でした。上の写真はたまたまワイフが撮っていたものです。
|
|
|
| 2011年9月28日 |
先日、ぼくが所属する松山教会で、東雲学園創立125周年を記念した礼拝があった。学園の創立は1886年(明治19年)である。

考えてみれば、それは日本にプロテスタント系ミッション女学校が次々に設立された時期と機を一にしている。そのほとんどがアメリカ人女性宣教師による設立であった。
当時、日本になぜ爆発的にミッション女学校ができたのか。その背景は、素人のぼくにもある程度理解できる。
主要な要因はアメリカの国内事情だ。19世紀半ばまでは、アメリカのフロンティアは西部にあり、国力は「西へ、西へ」に費やされていた。キリスト教の伝道も、それにともない西へ、西へと向かった。ローラ・インガルスの『大草原の小さな家』シリーズを読めば、その一端をかいま見ることができる。
一方また、南北戦争という大事件もあった。国が外に目を向ける時代ではなかった。
19世紀後半に入ると、アメリカ国内からフロンティアが消滅してしまい、人々の目が国外に向かい始めた。キリスト教伝道も同様である。プロテスタントのさまざまな宗派が海外伝道局を設けるようになった。
これによって、一般の職業に就くことを「女性らしくない」として事実上禁じられていた女性の「許される職業」が、教師のほかに宣教師にも広がることとなった。ローラ・インガルスは田舎教師になったが、宣教師にはそうたやすく誰でもが飛びつけるわけではなかっただろう。しかし、燃えるような信仰心とフロンティア精神と強い決意をもった女性は多くいたのである。
彼女らは所属宗派の伝道局や母教会から、資金面でも精神面でも十分な援助を約束されていた。だがそのためには、常に伝道局や母教会と緊密な連絡をとり、現地の状況を知らせ、支援を仰ぎ続けなければならなかった。その手紙書きが、彼女らの仕事の中でけっこう大きな比率を占めていたともいう。
といっても、女性は正式の牧師になれるわけではなかった(今はそんなことはないが)。宣教師の道を選んだとしても、彼女らにできるのは、教育・文化活動を通しての宣教だけであった。
というわけで、19世紀後半、日本に若い女性宣教師が次々にやってきて、宣教の手段として女学校を設立したのであった。一種のブームともいえる状況となり、1870年代、80年代の20年ほどの間に30数校ものミッション女学校ができた。
★ ★ ★ ★ ★ ★
こうした事情は、最近読んだ『ミス・ダイアモンドとセーラー服』(福岡女学院の例)や『アメリカ女性宣教師の来日とその生活』(金城学院の例)などで知った。
東雲学園(松山女学校)の場合は、事情が少し違うようである。設立当初には宣教師は直接かかわっていない。設立は、前年の1885年にできたばかりの松山教会が自ら行った。だから、初代校長は松山教会の初代牧師である二宮邦次郎がかねた。
アメリカン・ボードと呼ばれたアメリカの伝道局が経済面で援助を始め、宣教師ジャジソン女史が第2代校長になるのは1906年のことである。創設からすでに20年経っている。
といっても、松山教会自体がそもそもアメリカン・ボード(組合派の教会)の影響下で1885年に創立されたわけだから、それを思えば、東雲学園はアメリカン・ボードによる設立だと言っても、まんざら間違っているわけではない。だがやはり、創設は日本人の資金と手によるものであった。
東雲学園からやや遅れて1891年に松山教会の支援でできた松山夜学校(現在の松山城南高校)には、設立当初から宣教師ジャジソン女史がかかわっていた。
★ ★ ★ ★ ★ ★
ともあれ、当時はアメリカも日本も、社会が燃えていた時期だったのだと思う。「使命感」という言葉が、ごく自然に若者を包み込んでいた時代ではなかったか。
やがて日本は、日清・日露戦争を通じて帝国主義、軍国主義の時代に向かっていく。若者の使命感も、それに合わせて軍国調へと引きずられていく(大正ロマンの一時期をはさみはするが)。
今の若者に「使命感」はあるのだろうか。自分の喜びや楽しみ、仲間うちの喜びや楽しみという閉鎖的な枠を越えて、ある意味では自分を犠牲にしてでも、価値ある何ものかに向けて自分をささげる。これが使命感だろう。今の若者にはたして使命感はあるのだろうか。悲しむべきことに、今の日本の大方の流れの中には、この「価値ある何ものか」を見いだすのはなかなか困難なのではないかという気がする。
ファシズムの時代には、たしかにそれがあった。多くの若者がそのために命をささげた。しかし、それは外から与えられた価値、強制された価値であって、内から燃え上がる価値ではなかった。だからそれは本当の使命感に結びついていたわけではない。
いつの時代でも、若者は意識の奥底に、使命感を燃やすべき「価値」ある対象を切望する気持があるのだと思う。憲法改定を前面に押し出した安倍内閣の頃、「目的もなく、仕事もない時代だから、憲法9条を変えて戦争に行けるようになれば、それは大いにエネルギーが発散できて、すばらしいことだ!」と、こんな信じられないような意見が、街頭インタビューで飛び出していたのを思い出す。
戦争などという、文明と人道に逆行する方向ではなく、平和的で建設的な方向に若者がエネルギーを注ぎこめる「価値ある何ものか」は、今の時代、本当にないのだろうか。
|